Posts I like
- Chamillionaire/Reign Fall和訳
Chamillionaireが先日リリースしたEP、Reignfall収録のReign Fall Feat. Bobby Moon, Killer Mike & Scarfaceの歌詞を和訳してみました。所々おかしな部分もあるかもしれませんが、宜しくお願いします。
[イントロ:...

Chamillionaireが先日リリースしたEP、Reignfall収録のReign Fall Feat. Bobby Moon, Killer Mike & Scarfaceの歌詞を和訳してみました。所々おかしな部分もあるかもしれませんが、宜しくお願いします。
[イントロ:...

ライター : Ian Cohen
翻訳元 : http://pitchfork.com/reviews/albums/22526-american-football/
翻訳者 : kei
american footballはきっとこうなることを運命付けられていたんだろう。──彼らが休止して、10年以上もの時間を経た頃にソレは来た。american football、Braid、the Promis Ring──熱意と情熱と(しばしば、あからさまの無視)を批評家から受けていたlate-‘90s、Midwestern EMOは2010年あたりを境に、ようやく収穫の時を迎えた。そしてそれはアヴァンR&Bとかクールさとか、大学の中庭で景色を眺めながら涼むみたいなことにはどうにも馴染めないインディ・ロック・ファンにも好都合だった。新たな、育ちつつあったシーンとは無関係なとこから、彼らは還ってきた。数多のホープたちが自らの最高傑作をリリースする横で、2010年代にはフリークフォークもダンス・パンクも、もちろんEMOも現在のインディ・シーンの中で反響を起こすようなモノではなかったとしても。ただ、唯一にして、絶対の影響力を持つアルバムが彼らのディスコグラフィーにある。ジャズとポストロックを飲み込んで、削ぎ落とされたEMO。結成と解散を頻繁に繰り返したCapp'n Jazzのメンバーを中心としたバンドのファミリーツリー(訳注1)(Friend/Enemyとか、Owlsとか、Make Believeなんかだ)の1バンドだった彼らは、あのアルバムのみで自らを信じられないような高みへ──Hot Topicや、Warped tour(訳注2)なんかじゃない──導いてしまう正典となった。2016年の頭の頃にMike Kinsellaはamerican footballは「有名になる気も、それどころかバンドであることも」求めていなかったと言った。いま、そうじゃないと言っても首を縦に降るリスナーはいないだろう。なにより、きっと二枚目の『american football』以上に、僕らが待ち望んでいたEMOのアルバムはなかった。
Kinsellaの自身への評価のハードルは低すぎて、『american football(1st)』が生み出してきた神話をほとんど削り取ってしまう。二枚目のアルバムがリリースされたのは彼らがツアーを巡るのを楽しんで、同時に同じ曲ばかりを演奏するのに飽きたからだ。また彼はバンドの二枚目のアルバムがどれだけ望まれてきたのかも自覚している。「僕らはどこにいる?(原文 Where are we now?)」。21世紀になって初めてリリースされたamerican footballの曲で彼は問いかける。「ひとつ屋根の下で、僕らはひとりぼっち」──あぁ、そうだ、まるで二枚のアルバムカバーのようだ。今回、一つひとつのタイトルは歌詞の最初の一行からとられている。『american football(1st)』でソレは最後の一行だった。これは彼らについて話すなら大事なピースだ。
だけど、こんなどうしようもなく諦めの悪いファンがおもわずニヤついてしまうようなコミュニケーションは、一方で同じくらいのやきもきをずっと抱え続けることになる。m b v や、Wildflowerとか、Only Built 4 Cuban Linx…Pt.2(訳注3)とか、ね? 分かるだろう? 「Where Are We Now?」という一言は、フェスティバルの大観衆や数千人規模の会場に集ったファンのど真ん中へと投げ込まれた。一つの事実として、この曲のコーラスの存在がある──1stでは欠片もなかった要素だ、それはスポットライトを浴びながら、さざめくようなリードギターを相手にワルツを踊る。一言でまとめれば、後期のSunny Day Real Estateみたいなプログレッシブさだ。リード・シングルの「I’ve Been So Lost For So Long」にも最初のヴァースで鳴らされる4/4のドラム・キックがある。今では"the hit"と呼ばれ、ファンがキックに合わせて手拍子を入れるのがお約束になっている。Jimmy Eat Worldがかつて辿ったようなクロスオーバーの道をなぞるEMOの新星がいない中、この曲たちは問う。なぜ、僕らが僕ら(american football)のままであったらいけないんだ?
2年目を超えたリユニオン・ツアー以後のスケジュールや、ファイル共有アプリ上でのやり取りというセッションによって芽を出した彼らの2ndフルは、タイトな日程のレコーディングではあったものの、その熟練さと連続性を強く意識させる。彼らの二枚は並べてみると共に印象的だ。将来のぼんやりした不安に襲われて週末をダメにしたことだったり、Kinsellaが'16年頃からのバンドの変化は決して過去をないがしろにするようなものじゃないと明言したことを思えば、カラッと晴れ上がったようなプロダクションが『american football(1st)』の重くふさぎ込んだようなソレとの明確なコントラストを見せるのも、ジメジメとした晩夏の湿気を吹き飛ばす、秋晴れの空をわたる風のイメージに重なる。イリノイ大学の学院生だった頃よりは鋭さを増したソングライティングもその一因で、2つのギターが輪郭をなくしていくような摩擦はなくなり、「My Instincts Are the Enemy」で満員電車に押し込まれたPinback(訳注4)のように刻まれたり、どうにも薄暗いBサイドを「Disire Gets in the Way」でブン殴ったりする。つまりはそういう事だ、Kinsellaファミリーツリーの秘蔵っ子 Into It. Over It. がやらかしていることと同じ。
そして、数千人規模に膨れ上がった観客を前に用意されたものがある。力強さを増した構成、外さないサビ(Hook)、フルタイムのベーシストとして参加している(Mike Kinsellaのいとこ)Nate Kinsellaの存在。その一方で、ここに来てamerican footballは「= Mike Kinsella」としてメディアでは扱われている。バンドのアンサンブルによって語ってみせること、もしくは「Honestry?」「Stay Home」のその先でThe World Is a Beautiful Place & I Am No Longer Afraid to DieやFoxingの鳴らしたpost-emoを吹き飛ばしてしまうようなサウンドは聞こえてこない。ポップスターのようなミックスが施されたヴォーカルもあって、Kinsellaの存在感は圧倒的で、アルバムはウソみたいにキャッチーだ。かつての線の細いギターワークとひ弱なヴォーカルの代わりにMike Kinsellaの積み重ねてきたモノが収まった、もう分かってると思うけど彼の最も長命なプロジェクト、Owenのことだ。
これは当然で、別に間違っていない。Owenのコンスタントにリリースされたアルバムはどれも良い。僕が話したいのはディスコグラフィー中9枚のアルバムに、ほんの3ヶ月前(注 2016/6/27リリース。本作は2016/10/21リリース)、american football再結成後はじめてのOwenのアルバム『The Kings of Why』があるってこと。再結成というイベントがどこまで期待を煽ったかはハッキリしないけど、フルバンドによるアレンジ、ベル、笛、トランペットを同じように演奏できるプロデューサー S.Carey(訳注5)の起用──つまりもっともamerican footballっぽいOwenのアルバム。
ずっと首を長くして『american football(1st)』と肩を並べるようなアルバムを待ってるファンには悪いが今回もそう証明するものは見当たらない。僕もOwenのアルバムの「Empty Bottle」やVolcano Choir(訳注6)っぽい「Setteled Down」が、「I Need a Drink (Or Two, or Three)」とか「Holocene」みたいな「Home Is Where the Haunt Is」とかと根っこは同じものから生まれているんじゃないかって思うのはわかる。ハッキリさせたいのは、american footballの再結成/ツアーという流れは、真っ直ぐな曲構成のアルバムとなって、彼らの独創的なミュージシャンとしての立場を脇に押しやって進んでいる。そうして限られたスペースだとしても「Give Me the Gun」ではTortoiseの盟友、ご近所さん、はたまたSteve RichtやThe Blue Nile(訳注7)の門下生としてamerican footballは帰ってきたし、「Born to Lose」や「I Need a Drink (Or Two or Three)」のフェードアウトしていく終結部はヴェールの向こう側へ引っ込んでいく感情の陰影を淡いタッチで描きながら(「胡乱な目、なんて低俗なんだろう?」「乱痴気騒ぎから逃げられねぇ、僕は突っ伏すだけ」(訳注8) )、このレコードで最も下らない歌詞とハッキリとしたコントラストを生んでいる。
Owenでの彼がそうであるように、『american football』におけるMike Kinsellaは矛盾とすれ違いを抱え込んだ詩人だ。本人が認めるようにアルバムのマスタリング寸前まで彼は歌詞を書き直しながらレコーディングを続けた、 それが果たして良かったのか、確かめることはできない。そうして残ったフレーズは彼ららしい密やかさでマントラのように響くが(「Home Is Where the Haunt Is」)、一方で40にもなろう男がこんな歌詞を書いちゃうのかとこっちが恥ずかしくなるパートもある。つまりはBeach-Slang(訳注9)的な話なんだけど、James Alexのソロ・プロジェクトは彼の20代の思い出を今に伝えるのが目的で、じゃあKinsellaが哀しげに「ドクター、ここにいるのが痛くてたまらないんだ」とか、「淀んだ空のようにブルーな僕だ / 僕はこうやって死ぬんだ」と歌うのを僕らはまっすぐ受け取ればいいのか? それともEMOシーンの長老みたいな男、一流のジョークと笑えばいい?
こんな問いがバンドに与えるものなんて些細なことだ。『american football』はまだKinsellaが元Cap'n Jazzメンバーとしてしか知られていなかった1999年の話じゃない。彼にとって、「I’ll See You When We’re Both Not So Emotional」で語ったように、自分と自分のことばは相反するものじゃない。american footballというバンドは、その影響力と変わらずに秘められたセンチメンタルがあるにしても、サウンド面でもEMOとしても10代の終わりの頃の話じゃなくなった。『american football』の根っこに、いま大学の寮でヘッドフォンの間で耳を傾けている君に、「The One With the Wurlitzer」がフェードアウトしていく中でどれだけの季節が流れ、いくつの恋が散ったのかを写している。2016年現在、american footballのメンバーにはパートナーがいて、子供がいて、それなりにキャリアがあって、フルタイムの仕事がある。つまりは、不変だと思ってた目に映るセカイやモラトリアムの空想は思い出になるべきなんだ──Homer Simpson風に言うなら、このアルバムはラッキーにも日々の暮らしの中に30分ほど人生を振り返るチャンスをくれる訳だ。
訳注1 EMOの代表的バンド Cap'n Jazzのメンバーは以後もシーンを代表するバンドを結成、解散を繰り返していく。本文中で言及されているのはKisella兄弟を中心としたバンド達で、初期Cap'n Jazz期にサイドプロジェクトしてBraid、Gaugeメンバーと掛け持ちしていたThe Sky Corvairや、2001年にCap'n Jazzのオリジナルメンバーが再結成したOwls(その後Mikeの脱退によるメンバーチェンジがあったが、2013年の活動再開時にまたオリジナルメンバーに戻っている)、シカゴ周辺のアーティストが多数参加するFriend / Enemy(中心人物はTim、Mikeの兄弟とCalifoneのJim Becker、Joan of Arcにも参加しているTodd Mattei)、本文にも登場するいとこのNate KinsellaがJoan of Arcに在籍していた頃の別働隊として始まったMake Believeはこの中では長命のプロジェクトだったが2008年の3rd『Going To The Bone Church』とそれに伴うツアーをもって解散している。レビューでは触れられていないが、Cap'n JazzのVictor Villarreal(ギター)とSam Zurick(ベース)はインスト・バンド Ghost and Vodkaを、Davey von Bohlen(ギター)がthe Promise Ringをバンド解散後に結成する。
訳注2 HOT TOPICは北米を中心に展開するロック、ポップ・カルチャーをベースにした衣服、アクセサリー小売店チェーン。ライセンスによるバンドTシャツ、グッズを販売しながら、パッケージツアーのサポートも行なっている。Warped TourはVansが主催する大規模サーキットツアーで音楽、Xスポーツ、アトラクションが敷地内で同時進行で行われる。アメリカをはじめ、イギリス、南米でも国内を巡る形で開催されている。どちらもパンク、メタル、オルタナティブ・ロックのバンド/アーティストを中心としたラインナップだが、参加を断ったTouche Amoreを含めて、EMOシーンのバンドが参加することは稀である。
訳注3 それぞれMy Bloody Valentineの22年ぶりのアルバム『m b v』、The Avalanchesの16年ぶりの『Wildflower』、Wu-Tang Clanのメンバー Reakwonのソロ・デビューフルの14年ぶりの続編となる『Only Built 4 Cuban Linx…Pt.2』のこと。
訳注4 Pinbackはカリフォルニア州サンディエゴでRob CrowとZach SmithことArmistead Burwell Smith IV(Three Mile PilotやSystems Officerとしても活動中)を中心としたインディ・ロック・バンド。バンド名は映画「ダークスター」の主人公からとっており、初期のアルバムにはこの映画からのサンプリングが聞ける。Touch and Goを経て、現在はTemporary Residenceをレーベルとしており現在までに4枚のアルバムをリリースしている。初期と現在ではサウンドの印象は違うがどちらもamerican footballと共通する要素を備えており、Ian CohenはPoly VinylのレーベルメイトでもあるSunday’s Bestを引き合いに出して彼らを繋ごうとしている。
訳注5 S.CareyことSean Careyはウィスコンシン州オークレア出身のミュージシャン、プロデューサー。Justin Vernonのプロジェクト Bon Iverのサポート・ドラマーとしても知られており、自身も3枚のフルアルバムをリリースしており、 Sufjan StevensやTalk Talk、Steve Reichらと比較される音楽性で評価を受けている。
訳注6 Volcano Choirは前述のJustin VernonとCollections of Colonies of Bees(ウィスコンシン州で結成されたポスト・ロック・バンド Peleのメンバーを中心としたユニット)によって結成された、2009年にリリースしたアルバム『Unmap』一枚の為のプロジェクトだったが2010年に「最初で最後」という事で行った東名阪ツアーの出来に感銘を受けたJustinの意向を受けて、活動を継続。2013年に『Repave』をリリース、その後ツアーを行い、Bon Iverの活動に重心が移ったことにより活動休止となる。
訳注7 The Blue Nileはスコットランド、グラスゴーで1981年にPaul BuchananとRobert Bellを中心に結成されたロック・バンド。同じくグラスゴーを拠点とするハイファイオーディオ・メーカー Linnと関係のあったプロデューサー Calum MalcolmがLinnのスタッフに彼らのデモをスピーカー・テストの一環で聴かせたところLinnが設立しようとしているレーベルのアーティストにならないかと誘いを受け、1984年にレーベルの最初のリリースとして「A Walk Across the Rooftops」を発表することになる。続いて5年後にリリースした2nd「Hats」では高い音楽的評価とUKチャートで最高12位を記録する出世作となる。しかし。30年近いキャリアがあるものの非常に寡作で知られており(4枚のアルバムと関連したシングルが9枚)、2012年にPaul Buchananはソロ・アルバムをリリースしたが、2004年の『High』以降のバンドの動向は非常に不透明であり未発表のレコーディングを含め新しいリリースはない。
訳注8 筆者個人的な理解になるがamerican footballのアルバム、LP1とLP2はどちらも「出会いと別れ」が歌詞のテーマにあり、そのメインとなるフレーズは「すれ違い」だが、1stで大学生までの苦い記憶とそれぞれが未来へ進むための別れを選んでいたのに対して今作ではこの20年の間に置いてきてしまった人々の姿を描いている。これはリベラル的な自己責任論だがドラッグ、アルコール、仕事/友人の選択のいずれにおいても他人の選択に干渉することは他人の自己決定の能力を否定しているため、避けられる傾向にある。そうした境遇の改善のために福祉や厚生施設は用意されているがそちらを選ぶのもまた個人の自己決定の責任に応じる。つまり、この歌詞にあるように現状について不満を持ちながらも何もせず更に状況を深刻にする人々は放置されることとなる。そこをMike Kinsellaはこのアルバムにそうした状況をリユニオンとかけて持ち込んでいる。
訳注9 Beach Slangはペンシルベニア州で活動していたWestonでギター、ヴォーカルを務めたJames Alexがバンド解散後の2013年に結成したパンク/インディ・ロック・バンド。2枚のEPとスプリットをEMOリバイバル・シーンの中心的レーベル Tiny EnginesとLame-O Recordsからリリース後、Poly Vinylからデビュー・フル『The Things We Do to Find People Who Feel Like Us』をリリース。Jamesが影響を公言するThe ReplacementsやBig Starの音楽性とフィラデルフィアの音楽シーンを代表するアーティストのコラボプロジェクトとも言えるラインナップで、2020年に最新作『The Deadbeat Bang Of Heartbreak City』をリリースした。

ライター : Ian Cohen
翻訳元 : https://pitchfork.com/reviews/albums/the-world-is-a-beautiful-place-and-i-am-no-always-foreign/
翻訳者 : kei
そのイキったようなバンド名、10人を優に越えようっていうメンバー数、これまでも君の耳に入ってきたバンド達のようにThe World is a Beautiful Place & I Am No Longer Afraid to Die(以下、TWIABP)はユートピアンだ。彼らの言うEarth 2(訳注1)がどんなものなのか、2015年にリリースされた傑作『Harmlessness』から浮かび上がる。不安と恐怖が、それを消そうと君が灯したライトの生む影に隠れていることも、見捨てられた至る所で、それでも自分をなぐさめ、何かをなそうってやつらの手を取ろうとすることも、ローカルではあったけどあるフェミニストの復讐に「勧善懲悪」のラッパを鳴らしたことも。アルバムのオープナー「You Can’t Live There Forever」は2年後の今、いずれ訪れる終わりの残酷な序曲のようにも聞こえる。
例を挙げるなら、この曲でリードヴォーカルをとっていたD. Nicole Shanholtzer (訳注2)は2016年にバンドを去っている。つまり、彼らはここに来て自分たちのバンド名についてすら考えを改めなくてはいけなくなった。TWIABPの無視できないほどのエネルギーを秘めた3rdアルバム『Always Foreign』でメインのソングライターとなったDavid Bello (訳注3)はプエルト・リコとレバノン出身の両親と自らのバックボーン、ウエスト・ヴァージニアで過ごした日々を通して、そして今では不安と恐怖を見つめ続ける一人のアーティストして、きっと僕らと同じことを思っている。ーーこの世界はどんどんクソみたいな場所になってるし、僕らは襲いかかってくる死を怖がらなければ。
「なんもかんも僕がポリティカルなヤバい話にしてやるよ」。アルバムの頭でBelloは告げる。実際のところ、『Harmlessness』も2013年のデビュー・フル『Whenever, If Ever』も、今となってはそうとしか思えないような箇所が至るところに見える。それらはいつでも劇的なハッピーエンドを約束するロック・ミュージックだ。「この世界は美しい場所だ / でも、僕たちはぼくたちでやっていくしかない」。『Whenever, If Ever』を飾る永遠のクローザー「Getting Sodas」で彼らはそう歌った。その血統の中にある曲として『Always Foreign』のオープナー「I’ll Make Everything」は現れる。くたびれ果てた「愛のお話」を紡ごうとした曲は「The Future」でキラキラと輝く希望を描こうとして届かない。「未来がこうして今まさに手の中にある / 最低の今が、何もかもが過ぎ去ってしまう」。じゃあ、いま僕らにできることがあるとして何をしたらいいんだろう? これ以下は無いって思えばいいんだろうか?
大言壮語な理想論者が現実に対峙した今となってはTWIABPは極めて実際的なバンドとして語られるべきだ。サウンド面での話をするなら、『Always Foreign』の前半はこれまでにない速さで僕らがよく知っている場所まで駆け上っていく。「I’ll Make Everything」は眩しいくらいの未来を抱えているし、「The Future」はポップパンクのシーンを恐ろしい速さで駆け抜けていく。これまでのアルバムで終盤に用意されていたその光がもうこの時点で彼の中にある。そのシンプルな事実が僕らを眩まして、その影に隠れているものへと目を向けさせる。ギブアップしたいくらいの重苦しい空気に付き合わされることも、面白くもないセットリストも、いつまで経ってもやってこないライブのお楽しみも、最早ない。うん、そういうことが時たま見れたんだ(訳注4)、Shanholtzerがメンバーだった頃の彼らには。
Shanholtzerの不在はA面に並べられた曲のポイントとして輝いている。「Hilltopper」ほどに荒んだ曲(「悪魔にだってどっちが正しいか分かるさ、お前の身の程を知るがいい」)がTWIABPで聴けるとは思わなかったけど、そこに疑問の余地はないしーー「Dischord Recordに所属したR.E.M. (訳注5)」とまで呼ばれたバンドとして、このリリースは必然だろう。もう君にも分かるはずだ、彼らが何を語っているのかは。これは今ここにいる僕らと、これからとこれ迄の話だ。TWIABPの『Always Foregin』でShanholtzerの離脱と、ドナルド・トランプ (訳注6)の大統領選が時と場所を重ねて語られる。そのやり方はとても大事な議論の場から個人的な意見や政治的にショッキングな出来事の影響をできる限り排除しなくちゃいけないというシビアなもので、この2つが「Marine Tigers」でBelloが読み上げる告発状のコアだ。「全部の州がバラバラになっても、君はここをアメリカ(合衆国)だって言える? / 他人から何かを奪うだけだってのに、君はそれを仕事だって言える?」。だけど、アルバムが進むにつれて描き出されるものは特定の個人から、資本主義という社会の伝統的な問題点へとシフトする。「金儲けは最低の腐ったシステムだ」ってBelloは歌う、その頃にはアルバム名もまた違って聞こえてくる。
「Marine Tigers」の曲名はBelloの父親 Joséの最近出版された回想録から取られている。1940年代に移民としてニューヨークに移り住んだ彼の受けた差別とヘイトの物語だ。「見た目の違いというのは思ってるよりはっきりと私たちを浮き彫りにする。それは今も変わらない。子供の私は、いずれ僕もそうなるんだろうと思っていた、誰かを憎むのだろうと、そして、ソレはきっとニンゲンだろうと ( 原文 Color seemed to be the stronger divider of people. It still is. In my child’s eye, it became clear that if I was going to hate a race, it would have to be the human race)」、MVの最後をこの言葉が飾り、70年の時が過ぎて、Joséの息子はみんなも薄々感じてるようにそれが染み込んでいく様を見つめる。「新しく移り住んだ場所を歩いてみても / こころはどうしても落ち着かない / 何か夢が転がってるわけでもなくて / 似たような部屋に収まる」。この生活に張り付いた不快感は決してなくなりはしないし、この曲がこれまでのように咲き誇り、立ち上がることもない。内側から溢れ出るドラムロールと自棄っぱちのようなホーンの轟き、この数十年ずっと秘められてきた「ポリティカルコレクトネス」の火口から吹き上がるマグマだ。「Fuzz Minor」でソレに溢れるような彼らの冷めた目線が突き刺さる、盛り上がりもなければ頂点もない、ただヘイトが脈打つだけのような曲だ。「A-rabって呼んでみろよ / Spicって呼んでみろよ / お前が死んだ後どうなるのか待ちきれないぜ」とほとんど騒音のようなメロディーの一方で、分かりやすくターゲットが掲げられて、今の政府に対するある種の願望のまだ納得できる話かもしれない。
『Always Foreign』はTWIABPのリリース中もっとも取っ付きやすく、歌詞はどこまでも考え抜かれている。だが、その内側で流れるものは繰り返し聴いてもいまだに掴めない。『Harmlessness』よりも8分だけ短いこのアルバムは、けど、ふた回りは小さく感じる。これまで「The Future」ほどポップに振り切れた曲は彼らのセットリストには無かったし、「For Robbin」に匹敵するエモーショナルと率直な言葉に満ちた別れの曲をやらなかった、競技場を映す磨き抜かれた真鍮の輝きみたいな大人びた「Gram」も新鮮だ。けど、Belloが熱っぽく、思いの丈を綴るウエスト・ヴァージニアでの鎮痛剤の濫用の話は、Matt Berninger *訳注7 が生むような穏やかなホームドラマとは対極にある。
TWIABPのリリースはそれぞれが彼らがこの時代におけるインディ・ロック・バンドとして象徴的で、印象的なグループであることを示している。だが、どっかで誰かが言うようにここの所、彼らは更にその声を大きくしてる。もう、君も聞いたんじゃないか? 「君はこちらか、それともそっちか?」と、一連の流れを持ったシングル、EPのリリース、それを象徴する大きな変化を見せた一枚、内輪ネタ、カバー・ソング、リプリントされまくるTシャツ、無限に繰り返されるTwitterでのギャグ、その一つひとつでTWIABPはこちらに迫る。デビューEP『Formlessness』が持っていたのと同じくらいの輝きを持ってーー『Always Foreign』が迎えるのは決してハッピーエンドではないけれどーーコミュニティや変わっていくこと、僕らに対して変わらないモノを示し続ける彼らのアルバムが退屈であるはずがない。「この世界と僕」というテーマは『Always Foreign』で遂に仮定の話ではなく、リアルな意味を持った。友だちとより近く、肩を組み、混じり合わないものをどこまでも遠ざける。そうすれば彼らの「セカイ」はより小さくなる、だけど「君」ともう離れることはない。
訳注1 アメコミのDCコミック世界において、スーパーマンやワンダーウーマン、バットマンなどのヒーローが住まう架空の惑星。パラレルワールドとしての存在であり、作品によって扱いは違うが、世界史での戦争や事件などが過程は違うものの似たような結末を迎えている。ただ「Earth 2」が関わる作品は他にもあり、他の比喩も考えらるが訳者の印象としてこちらだと思い、訳している。
訳注2 このレビューにおいては、女性とされているD. Nicole Shanholtzer(原文リンク先での表記ママなのでIan Cohenの勘違い/引用、若しくは性同一性障害に対するトランスジェンダーへの配慮ではないかと訳者は判断している)こと、Derrick Nathaniel Shanholtzer-Dvorakはバンド創設時のドラマー、後にギター/ヴォーカルを担当(このアーティスト写真中央の人物)。自身が設立したBroken World MediaのレーベルからOne Hundred Year Ocean(同じく彼を中心にしたEMO/インディ・バンド、TWAIBPのメンバーも流動的だが参加している)としても幾つかEPのリリースがある。
訳注3 レビューにもある通り、プエルト・リコとレバノン出身の移民を両親に持つ、現メンバーでのフロントマン的存在、バンド加入は12年頃からで担当はヴォーカルだがマルチプレイヤーであり、以前からソロ名義でも作品をリリースしている。Thomas Diaz、Greg Horbal、前述のShanholtzerら結成、最初期のヴォーカル・メンバーが脱退して以降、実質のスポークスマンとして見られている。
訳注4 原文のリンク先でのセットリストは、ほぼ全ての時間が当日のShanholtzerの会場に対する不満と鳴らされ続けたハーシュノイズによって占められている。
訳注5 R.E.M. は1980年にジョージア州アセンズで結成されたオルタナティブ/インディ・ロック・バンド。オルタナティブ・ロック、インディーズ・シーンにおける最初期の重要バンドにして、ポスト・パンク、カントリー、ニュー・ウェーブ、ノイズ、フォークを消化したサウンド、政治的/文学的な歌詞とライブパフォーマンスで多くのバンド/アーティストに影響を与えた。また2004年の大統領選挙時にバンドは「Vote for Change」と題したツアーで持って、ジョージ・W・ブッシュに対してのキャンペーンを行ったが、結果としてはブッシュが再選を果たすこととなった。
訳注6 ドナルド・トランプは第45代アメリカ合衆国大統領、実業家。2016年大統領選挙で民主党代表のヒラリー・クリントンに勝利し、政治/軍事経験のない初のアメリカ合衆国大統領となる。「アメリカ第一主義(Make America Great Again)」「メキシコとの間の万里の長城」などオルタナ右翼(Alt-Right)とも呼ばれる賛否両論の発言が目立つが、このレビューにおいて重要なのは彼が「敵」を設定し、それに対するヘイトやアクションを持って自らに注目を集めるポピュリストとしてのあり方である。
訳注7 オハイオ州シンシナティで1999年に結成されたThe Nationalのヴォーカル、かつては広告会社に勤務していた時期もあるが、バンド結成の際に辞めている。The Nationalは現行USインディの最重要バンドとして見られ、最新作『Sleep Well Beast』はUSビルボード・チャート2位、グラミー賞のBest Alternative Music Albumを受賞している。また2008年の大統領選でバラク・オバマに向けて3rdアルバム『Alligator』収録の「Mr.November」をプリントしたTシャツを販売してサポートし、12年の選挙でもオバマ陣営の為の選挙サポートを行った。それ以外でも様々なNPO、組織へのチャリティー活動を行なっている。
付記
2015年に彼らがリリースした傑作『Harmlessness』はいまだ数千回はプレイに耐えうる凄みをその身に宿している。ただ、Ianがレビュー内で書いたように、物事を二面性(アイロニー)として描き続ける彼らの歌詞や曲のモチーフは「僕ら」の周りや、瞳に張り付いたものによって印象が揺らぐ。
告白する女性、ポピュリズム、人種主義、復讐を望まれる道具、因果応報、それらは2年後のいまになってみればシリアスだけどありふれた話に聞こえる。
同じようなことが『Harmlessness』に対して述べたPitchforkのレビューと、noiseyでIan Cohenが書いたレビューにも言える。僕がようやく「EMOリバイバル」の終わりに相当する気分になっただけかもしれないけど、今作『Always Foreign』でTWIABPは明確に自分の周りにある世界を見た上で曲を紡いでいく。メンバーの変遷によるサウンドの変化は1st EPのリワークである『formlessness(2016)』が示していた通り、ソフトなサイケデリアと静動の対比をよりコンパクトに表すようになった。そこにフロントマンとなったBelloの「二人の世界」に収まらなくなったメッセージは前作よりも更にEMOと呼ぶのすら難しい。本来、ここにあったはずのモノは僕たちが変えるはずだったセカイが僕たちを壊してしまうという矛盾を支えきれずに擦り減ってしまう。ケミカルな映えるジャケットも現実離れしたリアリティも全てビジネスの話にしてしまうなら、そうなることを望むのが「グローバリゼーション」じゃないか? そうしてどうなった? どこにも行けるからこそ、どこにも帰れない僕らにとっていまいる場所が「異邦(Foreign)」じゃないと、どうして言える?
「Marine Tigers」を何度でもいい、繰り返し聴いてくれ。「There’s nothing wrong with kindness / やさしさに間違いなんかない / There’s nothing wrong with knowing / 知ることに罪なんかない / We’re here, I told you so. / 僕らはここにいる、そう言っただろ?」。そうなんだ、いくら世界がそちらへと歩を進めようと。銃声がない日々も、涙の枯れる日も等しくいつか訪れる。ここではないどこかで、世界はそういう振りをする。だから、繰り返し聴いてくれ。記録されたことばを。
We are here, I keep to telling you so.

ライター:Ryan Dombal
翻訳元:http://pitchfork.com/reviews/albums/21332-blackstar/
翻訳者:トマトケチャップ皇帝
David Bowie は何度も死を経験したが、今また我らと共にある。彼はポピュラー音楽界のラザロなのだ。ラザロは聖書の登場人物で、4日死んだ後イエスの招きにより墓場から戻ってきた。Bowie も過去半世紀に渡り何人もの自分を眠りにつかせ、いつも異なる装いで戻ってきた。これはとんでもない光景であり、虚構を生きたというよりも、ラザロの帰還と続く流れ、僧侶たちが彼の話を恐れるあまり殺害を試みたことを想起させる。奇跡の人になることを想像してみるがいい、復活は神業としか言えない。
Bowieはこれら全てを知っていた。彼はいつだって1970年代に成し遂げた作品に対して応え続ける必要があったから。様々な種類のポピュラーカルチャーと実験的なカルチャーを産み出したあの10年間、彼は朝目を覚ますように容易く革新を続けた。80年代と90年代になるとかつての月日から逃れようとしたが、グレイテストヒットツアーとノスタルジーを経て、今や確固たる意志でかつての自分を掘り出そうとしている。そして計算抜きに吐き出すのだ。
ラザロと題された小劇場向けミュージカルには Bowie のアバターへのこだわりが見え隠れして興味深い。俳優Michael C. Hall が主演した本作には、Bowieからの影響を受けた最良の演技が見られる。ぶっ飛んでいて、飲んだくれで、1976年のアートフィルム『地球に落ちてきた男』に出てきた不死の異星人のような。マンハッタンの最上階を模したセットで、 Hall は摩天楼の窓を拭きながら Bowie の新曲『Lazarus』を歌い上げる。「この道にしろ、道が無いにしろ、僕は自由になる」と彼はガラス掃除で手を汚しながら歌う。「青い鳥のようにね」と Bowie も『Blackstar』の同曲で歌う。アルバムバージョンでは過去の残り香を実験的なJAZZとイカれた男たちのサウンドトラックの残響で取り戻そうとするようである。
トラブルに続く沈黙の数年を経て、 Bowie は2013年『The Next Day』を提げてポップの世界に戻ってきた。好意的な意見が彼の帰還に向けられたものの、アルバム全体に漂う停滞感を覆すことはなかった。これとは逆に『Blackstar』ではアイコンであることを捨て「何も失うものは無い」 68歳になったと『Lazarus』で歌う。このアルバムではモダンジャズのサクソフォン奏者 Donny McCaslin 率いるカルテットとの初共演がなされた。彼のレパートリーはハードバップから Aphex Twin のカバーまで及ぶ。 また Bowie の長年に渡るスタジオ協力者、Tony Visconti も伝統と歴史を引っさげプロデューサーとして帰ってきた。
『Blackstar』は David Bowie のレコードが他の何に似ているかという考えを揺さぶる。それはJAZZであり暗号であり本能でありドラマであり、過去作を抜きにしても異星人的だ。元々Bowie が最初に手にした楽器はサクソフォンであり、幼年期には異母兄 Terry Burns の影響でジョン・コルトレーン、エリック・ドルフィー、ビートジェネレーションのアイドルに夢中になっていた。 Bowie と兄弟とJAZZには重要な繋がりがあるのだ。Burns は生涯を通し精神分裂病に苦しんだ。彼は精神病院の窓から飛び降りを図った後、1985年には電車の前に飛び出し自殺を遂げている。
この事実はBowie がJAZZとサクソフォンを軽快に用いるのでなく、秘密めいた不安を示唆するのに使用した説明になると思う。彼は1973年の『アラジン・セイン (1913・1938・197?)』から2003年の『Bring Me the Disco King』に至るまでずっとアヴァンJAZZピアニスト Mike Garson を起用していた。1993年の『Jump They Say』では彼の野生的な演奏が Burns に捧げられている。だが何よりも1977年発表『Low』に収録された『Subterraneans』で聴かれるBowie のサクソフォンの息吹以上に悲しみが表現された曲はない。彼の作品中、最も陰鬱で感傷的で、この世離れした瞬間だ。あの曲が示した未来的なノスタルジー感覚抜きに Boards of Canada のようなバンドが出てくるのは難しかったろう。完璧な円環を為し、 Boards of Canada は『Blackstar』の特筆すべきインスピレーションとなった。この点において Bowie は自分自身から逃げられなかったことになる、だがそれは試みなかったことを意味しない。
タイトルの通り、今世紀に入ってからの諸作と同様に『Blackstar』は世界を覆うニヒリズムを取り上げている。2003年の『Reality』で彼は「生への希求と全てに終わりがあるという相反する考えに酷く混乱する」と物思わしげに言う。「この2つの想いが互いに争っている…この瞬間が真実だという気がする」。ぶつかり合いはこのアルバムでより強く激しくなっている。予想もつかないJAZZのソロと魂を込めたボーカルは合わさって緩やかな破滅についての普遍的なストーリーを紡ぐ。はしゃいだ感じの『Tis a Pity She Was a Whore』は17世紀の演劇から題を取っており、作中で自分の妹とセックスした男はキスの最中に彼女の心臓を突き刺す。 またBowie の倒錯したジェンダー観(「彼女は紳士的に僕を殴りつけた」)、騒乱、第一次世界大戦も取り上げられる。だが悪の根は全て同じだ−つまり何処だろうと何時だろうと人間は必要とあれば暴力に訴える。『Girl Loves Me』において Bowie は『時計じかけのオレンジ』のギャングが元ネタのスラングで叫ぶ。
JAZZと悪意と歴史の再現の混合は酩酊感があるが、『Blackstar』は2つの曲によって大団円を迎える。ここにおいてバランスは崩れ塩辛い涙にまみれた傷跡と血が姿を表す。これらは David Bowie の名曲に欠かせない要素だ。彼はマスクを脱ぎその背後にある皺が寄った皮膚と嘆きを垣間見せる。『Dollar Days』ではイギリスの片田舎で往時を過ごしたいと願いながら終ぞ落ち着けなかったことが告白される。「僕はバカな連中と離れたいと何度も何度も願った」と彼は歌う。言葉は『Blackstar』と今までのキャリアに向けた呪詛めいてもいる。そして『I Can’t Give Everything Away』で彼は再び苛立ったラザロのように戻ってくる。もはやこの永続的な苦しみは演技ではない。Bowie は死んだ後も生き続けるだろう。だが今だけは、 最後の復活を成し遂げ、神秘性をいや増し自分が作った神秘の中に包まれていく。
死を前にした時、人は何を思うのだろう。
全てが失われると知ってなお人を創作に向かわせるのが金やくだらない虚栄であるはずがない。
何を成し遂げたのか。何処に至ったのか。
人は死ぬ。だが死は敗北ではない。
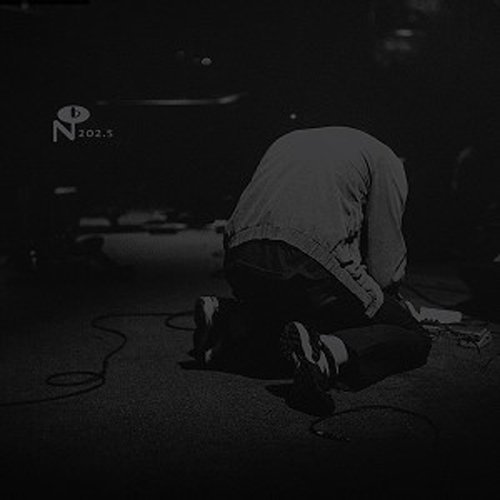
ライター:Evan Rytlewski
翻訳元:http://pitchfork.com/reviews/albums/20891-empire/
翻訳者:Gasse
90年代の終わりまで、Unwoundのメンバーはこのバンドが自分たちにとって戦い続けるに値するものかどうか、自問自答し続けていた。3人は、1998年のアルバム『Challenge for a Civilized Society』に過去最大の時間と資金を投資し、そのリターンとしてこれまでにないくらいの失望を味わった。前作の激しい叫びを、行き当たりばったりの実験的なスタジオ・ワークへと置き換えたこのアルバムは、昔からのファンを遠ざけ、彼らの出世作になり得た1996年のアルバム『Repetition』から積み重ねてきたバンドとしてのキャリアを断ち切ってしまったんだ。“『Challenge for a Civilized Society』が完成したとき、何人かの友だちに聴かせてみたんだけど、これはもう地べたから這い上がるところから再出発しなきゃって思ったのを覚えてる"。Unwoundの全キャリアを網羅した4作のボックス・セットの最終作『Empire』のライナーノーツで、ドラムのサラ・ルンド Sarah Lundが語っている。ベースのヴァーン・ラムゼィ Vern Rumseyは、“自分たちの作品の中では、一番気に入ってない作品”と評している。
もしUnwoundが『Challenge for a Civilized Society』をリリースして解散していたとしたら(実際そうなりかけたわけだが)、きっと今では忘れ去られたバンドになっていたに違いない。だが、彼らの伝説は揺るぎないものとして残った。初めの5枚のアルバム(※1)を通じて、彼らはカオティックなノイズ・ロックを磨きあげ、それによって永遠に記憶されるバンドとなった。彼らはNirvanaやFugaziのように広く評価されることはなかったが、彼らのDNAは、このバンドを発見し、影響を受けた若いパンク・バンドたちに何世代も受け継がれていくだろう。バンドの解散という選択を棚上げして、増え続けていく人間関係のいざこざと広がっていく物理的・感情的な隔たりを抱えながらも、ほんの少し無理を押してバンドとしてつくり上げた、彼らのラスト・アルバムにして最高傑作『Leaves Turn Inside You』(2001)は、決して忘れられないほどに美しい2枚組みのアルバムであり、このバンドに対する先入観・イメージを根本からひっくり返した作品なんだ。
『Empire』のメインとなるのは、10年以上の時を超えてヴァイナル盤としてリリースされた『Leaves Turn Inside You』であり、このバンドの最高傑作をもって一連のボックス・セット・シリーズが締め括られる。一方で、バンドのディスコグラフィの中では低い評価を受けている『Challenge for a Civilized Society』もまた、この機に聴き返す価値のある作品だ。言うなれば、これはUnwoundにとっての『End Hits』(※2)だ。無理やりにでもインスピレーションを引きずり出してやろうという望みのもと、スタジオに籠もりっきりになって産み出された過渡期のアルバムであり、部分的であるがそれは成功している。アルバムを通しての一貫性には欠けるものの、前作からは想像も出来ないようなUnwoundの音楽性の幅広さを、本作の楽曲から見て取ることができる。9分にも及ぶ曲「Side Effects of Being Tired」は、無骨なフリー・ジャズめいたサクソフォンの断末魔じみた絶叫で幕を開ける。テクノに対するディスである「No TECH!」では、Swell Map(※3)やThe Pop Groupといったポスト・パンク・バンドたちの強靭でしなやかなリズムを自らのものとしているし、「Meet the Plastic」の酔っ払ってがなり立てるような強烈なギターは、まるでUnwoundがJon Spencer Blues Explosionのアルバムをカバーしてるみたいに聴こえる。
好奇心にあふれたこのアルバムにおいて、1曲だけ明らかな名曲が存在する。「Lifetime Achievement Award」。バックで流れる「Happy Birthday」の上に、ファウンド・アート(※4)的手法で構築された、葬送曲めいたおぼろげで憂いのある曲だ。催眠術にかけられそうなペースと鳥肌モノの悲しみ。この曲には、『Challenge for a Civilized Society』のすべてが集約されている。パフォーマンス、ソングライティング、幻想的な音づくり、あらゆる感覚のすべてが、まるっきりタイプの違うレコードのムード音楽の類のようだ。
『Challenge for a Civilized Society』の売り上げは芳しいものではなかったが、BMGとの契約のおかげで資金面での余裕があった。そこで彼らは、長年夢物語として諦めてきたプロジェクトに着手した。自前のスタジオを設立したんだ。古い農場の地下室に少しずつ、少しずつ機材を運び込み、余裕がなくて買えなかった機材はキャルヴィン・ジョンソン Calvin Johnson(※5)に借りて、独学で使い方を習得していった。Unwoundはそれまでに、アルバムをセルフ・プロデュースした経験はなかったが、ラムゼィとギター/ヴォーカルのジャスティン・トロスパー Justin Trosperはがんばって、何週間もかけて技術的な細かい要素に取り組み、興味深いサウンドと構造を切り取る最良の方法を導き出した。いつものとおり、彼らは次々と製作を進めていき、失敗には目をつぶった。彼らは、実に贅沢な時間を手に入れたんだ。
彼らが製作に取り組んでいる最中に、かつて彼らのプロデュースを務めたスティーヴ・フィスク Steve Fisk(※6)が、進捗を確認しにスタジオを訪ねてきた。“何てこった、アルバムをつくるってのに、なんて最悪で陰鬱で惨めな場所なんだ、そう思ったね”。『Empire』のライナーノーツで、彼は過去のことをこう振り返る。あのスタジオは、『Leaves Turn Inside You』というアルバム全体に暗い陰を投げかけてる。8分間にも及ぶ、バラバラに砕け散った交霊会めいた悲しげな曲「Below the Salt」では、音と音との間に存在する“何か”が聴こえてくるだろう。同じように長尺曲の「Terminus」は、反逆の声明から始まるが、曲の中盤で、スタジオの壁の間を出たり入ったりする幽霊めいたチェロの音に導かれた絶望のオーケストラの前に屈してしまう。このアルバムは、まるで“永遠の11月”の中に閉じ込められているようだ。終わりゆく運命にある晩秋の日々。山々からはあらゆる色彩が奪い去られ、葉の落ちた木々と、冷え冷えとした孤独だけが残される季節。
この通り、 『Leaves Turn Inside You』は極めてメランコリックなアルバムであるが、同時に、尋常じゃなくすばらしいアルバムでもある。アルバムの1曲目「We Invent You」は、2分間にわたる警報音めいたドローンで幕を開ける。このやり方はおそらく、本作が自分の思ったような作品でないことを快く思わない古参のファンたちを、巨大な音塊とマルチ・トラックのサイケデリアでふるい落とそうとしたのだろう。ちょうどこの頃、トロスパーは『Led Zeppelin III』と出逢っていて、本作は彼なりのそのオマージュなんだ。メンバーたちの友人であるジャネット・ウェイス Janet Weiss(※7)(彼女は数年後にSleater-Kinney『The Woods』(2005)で、自身のクラシック・ロックの旗を高らかに掲げ上げた)が、 『Leaves Turn Inside You』ではもっともポップ・ソングに近い曲「Demons Sings Love Song」でバッキング・ヴォーカルとして参加していて、不穏な雰囲気に支配された本作の中の、華やかな小休止になっている。
『Leaves Turn Inside You』は決して、何もないところから突然生まれたものじゃない。世紀の変わり目の頃には、Radiohead、The Flaming Lips、WilcoそしてModest Mouseといった様々なバンドたちが、スタジオに籠もって、膨大な時間を費やして、後に傑作と呼ばれる冒険的なアルバムを製作した。しかし、それらのバンドたちが自身の成し遂げた成功をそれ以降も継続したのに対して、Unwoundが自らの成功を後に繋ぐことはなかったんだ。
このバンドの解散は、綺麗に表現するとすれば、彼らは最終作にして最高傑作である本作で全てを出し切って、そして終わりを宣言した、ということになるだろう。だけど、現実はそんなにロマンティックじゃあない。バンドは活動を再開したが、そこからゆっくりと崩壊へのプロセスをたどった、というのが実際のところだ。 『Leaves Turn Inside You』を引っ下げての過密なツアーは、肝心なところで“9.11”のために中断となり、さらにラムゼィのアルコール依存症が悪化したこともあって、もはや何事もなくこれまで通りに活動を続けることは不可能になった。本作のリリースから10ヵ月後、彼らは唐突にKill Rock Starsのウェブサイト上で解散をアナウンスした。14年が経った今でも、 『Leaves Turn Inside You』の衝撃は失われていない。だがしかし、このアルバムは守られなかった約束のように感じられるんだ。Unwoundの元メンバーたちが新しいバンドで元気に活動しているとしても、彼らがあのアルバムで見せた創造性や冒険心をもって取り組んだ作品は、あれ以降存在しない。彼らは新たな方向性を切り拓こうとしたが、それを徹底的に追求することはなかったんだ。
トロスパーは『Empire』のライナーノーツで、“今にして思えば 『Leaves Turn Inside You』における彼の自由連想法的な歌詞は、当時の問題を抱えたバンドの状況に関するものだった”とコメントしている。当時、バンドの人間関係は不安定な状態にあって、おそらくレコーディングを始める前には、終わりの予兆はあったんだろう。そして、たぶんこのアルバムがこれほどの傑作になり得た理由のひとつが、それなんだ。これは、幽霊についてのアルバムであり、 辛うじてメンバー3人が何とかひとつになってつくり上げた、バンドの最後の喘ぎなんだ。
【訳注】
※1 Fake Train(1993)、New Plastic Ideas(1994)、Unwound(1995)、The Future of What(1995)、Repetition(1996)の5枚のことか。
※2 『End Hits』(1998):Fugaziの5thアルバム。 『Challenge for a Civilized Society』と同じく98年のリリース。
※3 Swell Map(1972-80):イングランド、バーミンガム出身のポスト・パンク・バンド。活動期間中に2枚のオリジナルアルバムをリリースしている。【動画】
※4 ファウンド・アート、ファウンド・オブジェ: 既成の人工物を使用して製作される芸術作品。マルセル・デュシャン『泉』がその代表とされる。 https://www.google.co.jp/search?q=Found+object&espv=2&biw=1280&bih=699&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsmd-M9vbJAhVG_mMKHYEGD2oQ_AUIBigB&dpr=1
※5 キャルヴィン・ジョンソン Calvin Johnson(1962~): ワシントン州オリンピア出身の、ミュージシャン/音楽プロデューサーであり、インディ・レーベルK Recordsのオーナー。ミュージシャンとしては、Beat Happening、The Go Team、Dub Narcotic Sound Systemなどのバンドで活動。その他、Modest Mouse、Beck、Jon Spencer Blues Explosion、The Gossip、Built to Spillなどの作品に関わってきた。
※6 スティーヴ・フィスク Steve Fisk:ワシントン州を拠点に活動する音楽プロデューサー、スタジオエンジニア。関わったアーティストは、Nirvana、Soundgarden、Screaming Trees、Beat Happening、Lowなど。また、彼自身もミュージシャンとして、Pigeonhed、Pell Mellなどのバンドで活動してきた。
※7 ジャネット・ウェイス Janet Weiss(1965~):カリフォルニア州ハリウッド出身のミュージシャン。ドラマーとしてのキャリアが有名で、Sleater-Kinney、Quasi、Stephen Malkmus & The Jicksなどに参加した。
【訳者コメント】
ついに、Unwoundのボックス・セット・シリーズ完結です。今回の記事や、このViceの記事を読んで、Unwoundの全容がなんとなく掴めた気がします。しんみり切なくなってしまいましたが、それでも彼らが残した音楽のすばらしさはホンモノですし、この先もずっと自分にとって大好きなバンドであり続けると思います。
記事の翻訳が遅れに遅れてしまいましたが、何とか年内には間に合ったのでひとまずは胸をなでおろしています。また、Lomophy上のUnwoundの他の作品の記事もぜひ併せてどうぞ。

ライター : Evan Rytlewski
翻訳元 : http://pitchfork.com/reviews/albums/21037-harmlessness/
翻訳者 : kei
EMOはへたくそな歌声の上に成り立っているジャンルだ。そして、The World is a Beautiful Place & I Am No Longer Afraid to Die(以下、TWIABP)のデビューアルバム『Whenever, If Ever』はあらゆる意味でそういうモノを備えていた。叫び声、咽び泣き、震えた声のオンパレードで、ナード(Nerd)っぽさはどうしようもないし、曲にさらなる魅力を加えるためならバンド内の他のメンバーもどんどん使う。つまり、とことんハマるか、心底ムシするかしか僕らには手段がない。EMOリバイバルはありあまる、ゴチャゴチャの想いの丈がつきものだけど、彼らはまぁ、その中でもとびきりだ。今回この8人組バンドは'00年代のインディ・ロック全盛期的なサウンドに自らのEMOを染み込ませた。なのに、相変わらずTWIABPはニッチなバンドだ。
2ndアルバム『Harmlessness』で、バンドはメンバーを1人減らした(訳注1)。なんども繰り返したメンバーチェンジを経てある程度トゲというものを削ってきた彼らは、これまでにないラフさでアルバムの幕を開ける。問題はヴォーカルだ。叫び声が消えた。最前列に立つのは、事実上のバンドリーダーとも言える、David Belloのささくれやイラ立ちを押し殺した語り口だ。よりとっつきやすいヴォーカルを据えることでアルバムは整頓されたが、特に何かを失ったってことはない。曲は積み上げられ、壊され、悲しみがやってきて、祝福の鐘が鳴るーーときどきソレは数分の内に展開され、未だにバンドに節制の様子はない。それでも『Whenever, If Ever』より『Harmlessness』の方がウケるんじゃないかと思う。上品さを備え、より近しい感じを与えるのはリスナーのウケを良くするアレンジのおかげだろうーーただし歌声はあらゆる音の上にある、でもまぁ、例えば、君がストリングスの揺らぎを聞き取ることだってできる。TWIABPが向かった先はかつてのEMOバンドたちが辿った道に似ている。自分たちのサウンドを磨き上げる中で、逆に最初のころ自分たちが持っていた豊かさやセンスを活かせなくなるってオチだ。
彼らはレコードの頭に挑発的なトラックを放り込んできた。このアルバムで語るべきテーマを5分半に濃縮したトラック「January 10th, 2014」だ。"Diana the Hunter of Bus Diriver“(訳注2)について語るこの曲は名も知られていない一人の復讐者、メキシコ・フアレスでバスドライバー二名を射殺した女性だ。動機は深夜のバスドライバー達の中で常態化していた女性客への性的暴行に対する反撃だ。彼女は一瞬でフォークソング内のヒーローとなり、2つの市で賞賛された。バンドは「The American Life」の記事から持ってきたエピソードを当然のように歌詞へ放り込み、BelloとKatie Shanholtzer-Dvorak(ヴォーカル、キーボード)が互いのポジションを入れ替えてそれを演じている。Belloのドライバーとしての声は震えている。Dianaであろう乗客がさっきから、ようやく女性たちが襲いかかる野獣どもをねじ伏せるだけの力が持てるようになった、と話しているからだ。彼女は歌う。「ねぇ、あなた、怯えているの?」彼は答える。「ああ、そうだよ」ーー「そうじゃないと思う?」。
この瞬間はあまりにも出来すぎてる、ギリギリのミュージカルだ。僕らは聴いていて肌が粟立つのを感じるだろうし、たとえそっくりこのパートを剥ぎ取ったにしても、彼らの大胆さに驚くしかない。『Harmlessness』でもまず僕らに馴染むのはよく知った要素だーー倒れ伏した場所から立ち上がり、新しい道を誰かと切り開き、この世界に居場所を得るーーそれを今回TWIABPは捻じ曲げて、安全地帯になんか着地させず、僕らを最前線に引っ張っていく。生きることは世の中に従うことだろうか? 人生においてモラルと言う「おおきなもの」に僕らは全てを預けるのか、君は考えたことがある? この曲は殺人という最大のダブーを犯したことを認めながらも、Dianaの成したことに共感を示している。
慌てなくても、『Harmlessness』にももっと穏やかな話はある。Belloのこれまでにも聴いたような僕らを哀しみから引き剥がす曲だ。「Rage Against the Dying of the Light」はキャッチーなオルタナ風のリフを重ねて、アルバムの最高のハイライトへと逆回転を始める。少し老いた『Good News~ *訳注3 』時代のModest Mouseに通じる「Ra Patera Dance」を経て、「Harmlessness」は鮮やかに変わっていく。バンドのスマートなやり口はテンションを落とすことなく、刺激的なまま「Haircuts for Everybody」がわずか1分半で暴力的な祝砲をブチあげる。
デビューフルでは壮大な7分ものクローザー「Getting Soda」を置いた場所に、今回TWIABPは倍増しで放り込んできた(実際は2倍と半分だ、隠しトラックの小品が「Mount Hum」の後に控えてる)。やたらと壮大な展開を積み上げて、昇りつめる先はやっぱりヤリ過ぎ(overkill)だけど、曲ごとに見ればまだまだでもある。TWIABPが『Harmlessness』で成し遂げたのは、余計なものを全て削ぎ、美しさすら備えてこのどこまでも昇っていくアルバムを立たせるという荒技だ。
訳注1 彼らの非常に流動的なバンドメンバー構成的にどの時期との比較なのかははっきりとしないが、今作では前作『Whenever. If Ever』にチェロ、トランペットでクレジットされていた両名(ライブ映像に居たりしますが)、ギター、ヴォーカルだったThomas Diazはおらず、代わりにヴァイオリンとしてNick Kwasが加わっている。ちなみにfacebookで現在のメンバーとして紹介されているのは全部で9名である
訳注2 メキシコ北部の国境近くの町シウダー・フアレスで2013年8月末ごろに起きた匿名の女性によるバスドライバーの射殺事件。彼女は自らを狩猟、月の神 Dianaであるとし、事件の動機は深夜シウダー・フアレスとはリオ・グランデ川を挟んだ向かいにあるテキサス州エル・パソへと向かうルートに置いて常態化していた女性客への性的暴行への復讐である。彼女のメールでの言葉を借りれば「私はこれまで被害に遭った女性たちが求める道具である(原文 I am the instrument of vengeance for several women.)」
訳注3 ワシントン州オリンピアで結成されたModest MouseのEpic Recordからの二作目である4thアルバム。ドラマーのJeremiah Greenがこの時期バンドに不在だったため、Benjamin Weikelをはじめとして何人かのドラマーが録音に参加している。またThe Flaming Lips、The Dirty Dozen Brass Bandがゲストミュージシャンとして参加している。2005年のグラミー賞Best Alternative Albumノミネート、2007年にはプラチナディスクとなっている。
付記
今回このアルバムを3回だけ聴いて翻訳しました。個人的に一万回は聴いてもおつりがくるアルバムだと思うので残りの9997回も楽しめるでしょう。

ライター:Joe Colly
翻訳元:http://pitchfork.com/reviews/albums/16071-dive/
翻訳者:Gasse
Tychoことスコット・ハンセン Scott Hansenは、グラフィック・アーティストとして有名なんだけど、彼の音楽からもそのデザイン・スキルを聴くことができるんだ。彼の作る曲には、はっきりとしたロゴとかフォントみたいに、優れた縮尺と比率の感覚があって、それらをつくり上げるのには、明らかに多くの時間と労力が費やされてる。彼の手によるアートワークを見てほしい。彼のつくるエレクトロ・ミュージックを聴いて感じるのと同じものを感じられるだろう。1970年代にインスパイアされた、どこか懐かしさを覚える音景、深い静寂、そして遠く、手の届かぬ望み。そういったものがすべて、すばらしく滑らかなモダン・ミュージックと結び付けられている。こういった要素の中には、過去数年間のインディ・シーンにおいて打ち捨てられてきたようなものもあるのだが、ハンセンは、この『Dive』においてこれらの要素を、聴き手を惹きつけるようなやり方でうまく仕立て直しているんだ。
Tychoの曲は、主にシンセと生楽器のサンプリングでつくられていて、このエレクトロ・オーガニックとでも言うべきアプローチは、このジャンルの代表格であるBoards of CanadaとBibio(※)を思わせる。ハンセンは、彼らと同じような音楽的領域を探求していて、「A Walk」や「Coastal Brake」では、暖かみのあるセピア色のビートと華やかなアコースティック・ギターに彩られた安らかな平穏さに釘付けになってしまう。Tychoと、同じような音楽領域を探求する凡百のベッドルーム・ミュージックとを分かつのは、単純に言ってその技術にある。このアルバムの曲はどれも、強迫性障害レベルの細部へのこだわりをもってつくられているんだ。パーカッションの音を聴いてみよう。インディ・アンビエント初心者の多くは甲高いシンセ・ビートを好むが、ハンセンは本物の生ドラムの鋭く高い音から重く鈍い音までをサンプリングするのに細心の注意を払ってる。それは、聴き手に自室でドラムが演奏されているかのように感じさせるレベルだ。
ハンセンの細部への心配りは、個々の楽器のレベルにとどまらない。楽曲を組み立てていく中で、ハンセンはシンセの音とパーカッションの脈動とを自然な弧を描くかのようになじませていく。例えば「Daydream」は、きらめくギターの音と力強く打ち鳴らされるビートともに極めてシンプルに始まるが、曲の進行とともにその拍動は早まっていき、曲が終わる頃にはタイトルどおりの性急さが感じられるようになる。ハンセンは明らかに、この曲にヘッドフォンで聴いたときの深みを求めているし、こういう微妙は変化はいつまでもリスナーの関心を引くことができる。そして、彼のつくり上げた心象風景の中には、 平原や牧草地、静かな海などあらゆる光景が存在し、聴き手の脳をいともたやすく「リラックス」モードにセットし、これらの自然の風景を魔法めいて現出させてみせるんだ。
このすばらしく手の込んだ静寂こそが『Dive』の最大の売りだとすると、それは同時に、緊張感を欠いたしつこさという本作の欠点をも露わにする。ハンセンは、アルバムの全ての要素を穏やかにしようとするあまり、危険やリスクを作品の中に加えることを良しとせず、結果としてこのアルバムは時折、少しばかりの単調さを感じさせる作品になってしまった。突然の曲調の変化とか、暗い雰囲気を時折交えるとか、そういったことで本作はもっとバランスの取れたより面白い作品になったはずなのに。驚きという要素が欠けているために、TychoはBoCとかBibio(前者にはもっと非現実感があるし、後者にはより冒険的なポップさがある)などと同じ高みに達することができないのだけど、ハンセンは最終的に自らの試みには成功しているんだ。『Dive』は歴代最高に野心的なインスト・アルバムとはいえないかもしれない。だけど、おおよそ名盤と呼ばれるにふさわしい作品だと言っていい。
【訳注】
※
・Boards of Canada(1986-):スコットランド出身の、マイケル・サンディソンとマーカス・イオンの2人によるエレクトロニック・ミュージック・ユニット。
・Bibio(2005-):イングランド、ウェスト・ミッドランド出身のスティーヴン・ウィルキンソンによる エレクトロニック・ミュージック・ユニット 。
Lomophyへの記事の投稿がずいぶん久しぶりになってしまいました。。。ふんわりとやさしいエレクトロ/ポスト・ロック・アルバムです。 このアルバムを愛する友人に、この記事を捧げます。
*この記事はEchoes and Dustの了解の下、翻訳・投稿されています。
It would be allowed to translate and show by Echoes and Dust.

ライター : Mark Martins
翻訳元 : http://echoesanddust.com/2015/08/interview-philip-jamieson-from-caspian/
翻訳者 : kei
12年、4枚のアルバム、3つのEP、そして、スプリットとライブアルバム 。ポストロック・シーンにおいて最も多くの、幅広い賞賛を浴びるバンドにCaspianはなった。その裏には数々のエピソードとトラブルと成功が詰まったキャリアがある。
もはや彼らは悠々と新作『Dust & Disquiet』を携え、前作『Waking Season』で飛び越えたジャンルの壁の向こう側に、3年ぶりに歩を進める。初期の作品(『You Are The Conductor』や『The Four Trees』)からははるか遠くの話だ。
私ーーMark Martinsは、今回Philip Jamieson(ギター、シンセサイザー、キーボード)にインタビューを行った。来たるべき4枚目のアルバムについて、それを引っさげてのツアー、それに彼らと彼らのこれまでについても。
・やっぱり、まずはアルバムについてからだと思うんだ。新作『Dust & Disquiet』についてもうちょっと詳しく聞かせて欲しい。もしこれから誰かに聴かせるなら、君はこれをどうやって紹介する?
Philip Jamieson(以下、Philip): これまでとは地続きではあるけど、大きな発展があるんだ。新しいアルバムもドラマティックで、感動的でエモーショナルなレコードだ、でももうちょっと陰影や明暗のキレ、曲ごとの個性がはっきりしてる。Caspianの作品っていうものにあるべき要素は一つも欠けてない、と僕は思ってるけど、これまでとは明確に線を引いて欲しい。それが僕らが大事にしたいことなんだ。このバンドのスタイルはありつつも、誰もが挑戦することや変化することを止めたくはないんだ。
・アルバムの制作にあたって何か影響を受けたものは(音楽的に、それ以外にも)あるのかな?
Philip: 今回のアルバムでは音にヘヴィさを求めた、それにサウンド面で滑らかさよりも刺さるカタチにする為に剥ぎ取ったものもある。僕自身にはこのバンドやアルバムが創作の元になった、と言えるものは無いね、ただこれまで聴いてきたものが集まっているのは間違いないよ。

・君にとってお気に入りのアルバムの曲は何かな?
Philip: うーん、逃げるわけじゃないんだけど、それはすごく答え辛いね。サウンド的にも、エモーショナルの面でもそれぞれの曲に色々な印象があって、それらが結びつけているものも全く違うんだ。「Rioseco」は聴くたびに胸が締め付けられ、アガりたい時なら「Arcs of Command」がこれ以上ないほどにハマる。落ち着いたり、深く沈み込む時には「Equal Night」をリピートするだろうし、「Run Dry」は今までのどんな曲よりもその奥にある思い出を引っ張り出してくる。なぁ? 全く難しい話だろう?
・レコーディングについてもうちょっと聞かせて欲しい。君たちはこれをライブ録音でやったのかな? それともパート毎に?
Philip: ニュアンスとか、細部にこだわるようになってからはずっとパート毎に録音してる。自分たちのパフォーマンスをちゃんと残そうとしているけど、その為には最高のテイクが録れるまでやる必要があるんだ。
・そうしたモチベーションはどこから来てる? なにが君を熱くさせてる? それに自分たちの作品に熱くさせられることはあるかい?
Philip: 僕が思うのは、誰であれ自分たちのやってることに(僕らはすこしやり過ぎかもしれないけど)入れ込んでるアーティストってのは同じなんだよ、自分の曲を聴いてブチ上がることもあるし、耳を塞ぎたくなることもある。ある時は世界中のなによりも面白く楽しめるけど、別の日には一音たりとも聞きたくなくなる。これって当たり前のことだと思うんだ、もしなにか生み出したり、作り上げていくのなら、そこには向き合うことと関わり合うことがどうしても生まれるはずだ。自分の人生の中で費やすものなんだし。僕はそういうもんだと思ってやってきた。モチベーションについては、たぶん僕はすごく大きいところから来てると思う、そうこの星すら内包してるこの宇宙とか、そういう大きな目線で見たときに僕を突き動かすものがあるんだ。そうした体感的なものを共有できる人がいるのは大事だし、それと僕が本当にいいと思ってるのがビーチに出かけて行って波間を何時間でも漂ったりすること。最高に気持ちいい状態なんだ。
・今まで一度も生でCaspianを見たことない人がどういうイメージをそれに持っていると思う? 君たちがコンサートで望む反応ってのはどういうもの?
Philip: 僕らのショウはどうしたって最後には感情に任せた爆発に飲み込まれてしまう。いつも待ち構えているその爆発が、僕らもそうであるように、純粋の心の深いところから来てるんだって感じてもらえたらいいと思ってる。僕らの感情の動きにはフィジカルな面も常に色濃く出てくるし、毎回、60〜90分の演っている間はみんなドキドキしている。僕らはその時々で自分たちにできる最高のサウンドを求めて、表わそうとするけど絶頂にあるって感じられるのはせいぜい、そのショウの中の"まばたき"くらいの間だけだ。でも、その瞬間だけは全く違う。これまでの自分とか、今どこに居るかとか、何もかも消え去って……そこに全てがあるんだ。僕はたぶんその瞬間を目指して生きてるし、その為ならプレイする時間が30秒でも構わない。
・君たちはこれまでに様々な国をツアーして来た。ツアーをすることの価値ってなんだろう? それとそうした中で出会った人や文化で何を学んだと思う?
Philip: 僕らは40か国以上、全部で650くらいのステージをこれまでプレイしてきた。そうした日々では、一日の最後にステージの上で観客を眺めているんだ。何回も行った国もあるけど、その度に観光したり、新しい経験をしたり、まぁそうしたものに見慣れたりする。でも、そうするとまた自分の中にエネルギーが湧いてきて、なんでわざわざそこまで出ていったのか思い出すーーただただ素晴らしいショウをしたいんだ。そうやって年を経てくると気づくんだけど、自分の中にアメリカの暮らしではあった物が無くなったりしてるんだ。シャワー、ベッド、キッチン、自分の部屋にあった物とか。そうやって変わった中で、この数年は拍手と歓声に包まれることもできるようになったんだ。でもその裏で思うのはそういう身分の人間に自分が成ってるんじゃないかってこと、つまり重箱の隅をつつくような文句も言えるくらいの。そういうのは本当に不愉快だし、そうなってたら最悪だから、自分をちゃんと見張ってるんだよ。もし僕がこれまで見たものから学んだものがあるとするなら、人間はどこに居たって変わらない、一人ひとりを見れば同じやつはいないけど、君が思うより僕らはきっと似ている。
・このバンドのメンバーはみんな別の仕事を持ってるの? それともCaspianにだけ携わってる?
Philip: 僕らは全員が普段は別の仕事をしているよ、Caspianの活動は全然お金を生んだりはしないから。
・君にとってここ最近お気に入りのバンドっている?
Philip: すまないけど、ここ最近新しいバンドや曲ってのを全く聞いてないんだ。自分でも理由はわからないけど、いま周囲にそういったものがないんだよ……うん。
・バンドの歴史で一番面白かった、それか恥ずかしかったコトってなにかな?
Philip: 1年前かそこらにマニラで小人とボクシングの試合をしたんだよ、僕は190cmくらいあるんだけど気づいたらリングの上で寝ていたね。

ライター : Ian Cohen
翻訳元 : http://pitchfork.com/reviews/albums/19851-dads-ill-be-the-tornado/
翻訳者 : kei
それはちょうどアルバムの真ん中辺りだ。Dadsの2ndアルバム『I’ll Be the Tornado』でJohn Bradleyは吠える。「俺は幸せになりたいんだ / そういう自分を押し殺すんだ」。どれほど曲を重ねようと彼の言葉はこれに尽きる。あまりにも素直で、分かりやすく、その意味するところは明らかだ。カナダ・ニューブランズウィック州出身 *訳注1 の二人組、Dadsはこれだけで語っていいのなら彼らの人生と言えるーー抱えきれないほどの感情を積み重ねながらも世間の多くの人と違うところは全然ない。Bradleyの言葉で言うならこうだ、「結局俺に自分一人のケツを拭くだけの金もないなら / 一人ぼっちで死ぬことにビビることもないはずだろ?(原文 If I can’t even afford a grave for myself/ Then why am I so afraid of dying alone?)」。
よくある事だけど、Dadsも自分たちのやることや、ツアーする時のブッキングなんかで語られる。つまり、「シーン」のことだ。パンク〜ハードコアでこれまで「シーン」として語られるものの存在は大きい。だから、Bradleyが「幸せ」を求めるなら無視できるものじゃない……そうなんだけど、それは「本当」とか「現実」とはまた別の話だ。自分たちこそがこのシーンのあり方を体現してる、なんて考える人たちが集まると大体がどうしようもなくなるもので、Bradleyが「You Hold Back」で歌う言葉が印象的だ。「自分に絶対の才能でもなきゃ、みんなの意見に逆らうなんて無理さ」。これは「シーン」についての批評でもある。多くのバンドがそうしたものは難しいモラルについての話として半ば棚上げする横で、彼はコレは自分たち一人ひとりの問題であってこれから先どういう道を選ぼうと避けることはできないものなんだって苦々しくも認める。これは彼が何もしない自分を責め立てることと重ならない、だけどDadsとしてソレは丸ごとこの絞り出したように濃い、先に向かおうとするアルバムに表れてる。
このアルバムはどっから見ても変化についてだ。彼らについて一目でわかるものがあるから、サウンドより前にそっちを話そう。アルバムのタイトルとアートワークについて。2012年のデビュー・アルバム『American Radass(This is Important)』にまざまざと感じられる汗くささから、2013年の憂いのある洗練されたEP『Pretty Good』までをざっと眺めてからもう一度、このスタイリッシュで抑制された『I’ll Be the Tornado』を見てみよう。色んなものを見てきた人間なりに言わせてもらえば、Dadsは架け橋だ。影響を受けたものへのリスペクトを忘れず、でも決してその後を歩くことなく、言葉にはしないけれでも ‘90年代のEMOは決して「正しい」パンク/インディ・ロックと呼ばれるものから切り離されたところで起きたものでは無いと問うている。二人組になってから、ギタリストのScott Scharingerはリードギター、リズムギター、そしてベースの役を一人で担ってる。彼による、Mineralやamerican footballを思い起こさせる、滑らかでメロディックなフレーズはサウンドの重要な位置を占める。だが、Dadsにあるのはそれだけじゃない。一発で観客の心をつかむパワーコード満載の、誰もが大声で歌ってしまうメロディー(「Chewing Ghost」)、コール・アンド・レスポンスで畳み掛けるサビ(「You Hold Back」)、ジャングリーなカレッジ・ロック(「Take Back Today」)の質感もある。短距離走者のように駆け抜けるドラムを叩きながら、Bradleyのヴォーカルは鮮やかにミックスを貫いていく。それはthe Promise RingとBraidにModest MouseとLes Savy Fav *訳注2 を結びつけたかのようで、ヘロヘロなスタイルと衝動に任せたミュージシャンシップのどちらでもありどっちでもない。こういうのが数年に一回くらいインディ・ロックの中から出てくる。
だけど、もっと大事なのはこれからだ。Dadsの自分自身との対面における痛みを受け止めているもの、それが歌詞だ。今年度のーー前回はWaxahatcheeが『Cerulean Salt』 *訳注3 で手に入れたーー『The Execution of All Things』 *訳注4 を最も受け継いだアルバム・アワードは『I’ll Be the Tornado』に送りたい。言葉を変えるなら、彼らの行く先は、一つじゃないかもしれないけど、これからLiveJournalやMySpace、Twitterに積み重ねられていく膨大な言葉の中にこそ表れていくんだろう。Bradleyの歌詞はそれほど詩的でもないし、インテリっぽくもない、大きな問題にコミットするんでもない。だけど、僕らの人生にふと訪れる瞬間をほとんどそのまま持ってきたように描き出す。上手く演出されたコントのようにそれぞれにドラマが潜んでいる。「But」でBradleyは恋人とだけ通じるジョークを求めるシーンはとても甘い、でも逆にオープナー「Grand Edge, MI」のアコースティックな前半は張り詰めていて、彼はつぶやく「君に俺のこれまでを伝えたい……君には俺の全部を教えたいんだ」、そうやって感傷が滲み出てくる。分かるだろ? 誰にも言えない秘密があって、それを伝えてしまいたい。でも、その結果としてこれまで失ってきたことが声を潰すんだ。きっと、それはまだ今じゃないって。
アルバムを流していると、ふと矛盾を感じてしまう。『I’ll Be the Tornado』のあまりの人間臭さとその訳は僕らがBradleyは結局いいヤツなのか、それとも単なるクズなのかいつまでも言い切れないからなのか。「Take Back Today」の中で彼は告げる「君をここまで連れてきてオヤジに会わせてみたかった / 彼が痛みにもがいたりせず、医者が何かを始める前に」。それはシーンが注目のバンドとしてイケイケな姿(「俺が住むことなんてなかった街の夕日を思い出す / ちくしょう、今にみてろ / いつかそこをホームにしてやる」)と噛み合わない、でも短命ながらシーンを次に導くのはいつだってそんな奴らだ(「俺も争ってる奴らと同じ場所に行った / そこなら大事なものがあると思った / 君は俺にはどうしようもできないことばっか教えてくれた」)。
結果として、荒野に佇むことはBradleyのパーソナリティーに大きな意味を持った。「But」と「Fake Knees」はゆっくりと盛り上がりながら、そのピークに君と僕の両方が抱える不甲斐なさを抱きしめるという苦味を置いている。「Fake Knees」では、パートナーのうざったるい小言や本質的な二人の関係の問題がBradleyの頭を蝕む、あぁ、もしかしたらこうやってどうしようもなくなるのかもしれない、ふと頭をよぎるのは汚いTシャツに囲まれて二人で寝たことや、「服の山の上で泣きはらした目をしながら叫んでたんだ」っていうこと。でも、冷たい、残酷な答えはどうやってスッパリと切り離すべきかってことなんだ。「Chewing Ghost」は左のほおを差し出しながら、いざとなったら君をぶん殴るように居座っている。コーラスでの爆発の前にBradleyは吐き捨てる、「敵がやってきて、敵は追い払う / 痛い目も見たけど大したことじゃないんだ」。「Enemies」と「memories」が、この曲のアタマで「punk」と「drunk」が重ねられるように歌われるのは偶然じゃない。これはどう考えても一緒じゃないけど、Dadsの中ではこの2つを切り離すことはできない。
7分に及ぶポストロックの残響と言える「Only You」はなんというか「カッコいいクローザー」っぽさが強いけど、 いい感じに力が抜けてる。ここに向けてBradleyは過去を押しやる自分に気づいて(「俺は別に墓なんて要らないんだ / そんなものは踏みつけてくれ」)、「あの時のことを忘れたいって、未来の俺は望むはずだ」。最後に曲名が現れる「Take Back Today」、きっとこのタイトル自体が彼なりのアドバイスなんだろう、君の理解や彼の経験なんかを超えたところにある、たったひとつの。別に僕らに過ぎ去ったどうしようもない過去や友情、心地よさなんかを振り返ったりしながら、オトナぶって経歴や人生をコントロールするヤツになれって話じゃない。君は自分自身であればいい、『I’ll Be the Tornado』はセカイに対してDadsのクソったれな話を確信と自信を持って鳴らしている。
訳注1 Ian Cohenはニューブランズウィック州出身と説明しているが、wikiや彼らのバイオグラフィーによると彼らは2010年にニュージャージー州ピスカタウェイで三人組のバンドとして結成された。その後、具体的な時期は不明だが活動のしやすさを重視してJohn BradleyとScott Scharingerのデュオとなる。
訳注2 the Promise Ring、Braid、Modest Mouseについては以前の記事の訳注を参照して下さい。Les Savy Favはポストパンク/ポストハードコア/インディ・ロック・バンドであり、1995年にロードアイランド・デザイン・スクールで知り合ったメンバーによって結成される。Fugazi、Jawboxなどに代表されるポストハードコア、ノイズロックやアートロックに影響を受けたサウンドとヴォーカリストのTim Harringtonのライブ・パフォーマンスで有名。2007年に発表した『Let’s Stay Friends』はPitchfork、NMEをはじめとした多くのメディアから賞賛を受けた。
訳注3 WaxahatcheeはKatie CrutchfieldがP.S. Eliot(双子の姉妹であるAlison Crutchfieldと結成したポップパンク・ユニット)として活動中に開始したプロジェクトで、2011年にP.S. Eliotが解散以降の彼女のメインプロジェクト。EMOの枠にも括られるパーソナルな歌詞と、オルタナティブ・ロックとフォークがかけ合わさったサウンドが特徴。2013年にリリースした『Cerulean Salt』はモラトリアムの終わりと取り戻せない過去をテーマにし、Pitchforkでの8.4や、10年代のベストアルバムへのランクインしている。
訳注4 『The Execution of All Things』はロサンゼルス出身のインディ・ポップ・バンド Rilo Kileyが2002年にSaddle Creekからリリースした2ndアルバム。女優としても活躍しているヴォーカル/ギターのJenny Lewisの子供時代の思い出をテーマにしたアルバムであり、彼らの名前を知らしめたアルバム。

ライター:Sasha Geffin
翻訳元:http://pitchfork.com/reviews/albums/20685-katie-dey-asdfasdf/
翻訳者:Gasse
音楽ジャンルは、まるで行政区の区割りのように分けられてきた。ポップ・パンクの叫び、ポスト・パンクの呻き、ドリーム・ポップの囁き、そしてメインストリームのスターたちの明瞭できれいな歌声、みたいな感じで。ケイティ・デイ Katie Deyは、ファースト・アルバム『asdfasdf』によって、この“ヴォーカルの地理学”からは異質な立ち位置を確立した。彼女はメルボルンを拠点とするシンガー・ソングライターであり、どの曲を聴いても、彼女のヴォーカルには腐蝕処理が施されているように聴こえる。多くのホーム・レコーディングの作品には、リアルな言葉をリアルなマイクを通してリアルなテープ・レコーダに吹き込んでいるようなイメージがあるが、この『asdfasdf』はそういうイメージを抱かれることを拒絶する。このアルバムに収められた7曲は、おおよそ物理空間で産み出されたようには聴こえない。カオティックで、ざらついていて、音声の忠実度をまるっきり古びたものにすることに、全力でエネルギーを注いだかのような作品だ。
デイと同じOrchid Tapesのレーベル・メイトには、彼女と音楽的にとても近しいアレックス・G Alex Gがいる。彼女もまた、ピッチ・シフトと独特なチョイスの楽器を駆使してぶっ飛んだインディ・ポップを撒き散らすミュージシャンだ。音楽において、女声ヴォーカルは特に耳障りなうるさいものが排除される傾向にあるが、だからこそデイは自分のアルバムを極端なレベルまで耳障りなものにしたんだ。アルバムの1曲目「don’t be scared」では、クリーンなアコースティック・ギターのリフと不安定なドラム・ビートの間から、理解を超えたレベルのハイ・ピッチに加工されたしゃがれたヴォーカルが聴こえてくる。曲の後半では、デイのヴォーカルのトーンに似せたシンセサイザが奏でられ、彼女の言葉の輪郭がぼやけてあいまいになり、人間と機械との境界線が不鮮明にぐらついて、彼女が、自身のヴォーカルにはもちろんのこと、まるで彼女の奏でるすべての音楽の中に存在しているように感じられる。
『asdfasdf』で最も際立っていて、エネルギーに満ちた曲は「unkillable」で、絶えず脱線しそうになるふわふわとしたメロディを持った1分20秒の歌だ。デイの歌詞はここへきてとても透き通った輝きを見せ、“10代のポエトリ teen poetry”とか“私の足から流れ出る血を舐めて suck the blood from my feet”みたいなフレーズが、奇妙で幽かな一瞬の光となって輝くんだ。この曲は、なにもかもおかしいのに、キャッチーだ。曲の大部分はスムーズに受け入れられるようにデザインされているが、このデイのナイトメア・ポップを聴くと、なにやら尖った危ういものを飲み込んだような気分にさせられるだろう。この曲のタイトルは、その“もじり”の元となった言葉を連想させる。つまり、“unlikable(好ましくない)”ではない、ってこと。最初にタイトルを見たときには読み間違えてしまうかもしれないが、実際には力強く、抑えの効かない、無敵の曲なんだ。
デイは決して、ぶっ壊れた曲づくりを自らの武器として使う初めてのソングライターというわけではないけど、“あたりまえ”をひっくり返すことに悦びを感じているのは明らかだ。とかくヴォーカル、とりわけ女声ヴォーカルというものは、特に静かで穏やかな曲においては、美しく、わかりやすいものであることが望まれる。デイは、持ち前の荒削りな攻撃性を増幅して、テープ・マシンの中の空間を引き裂き、その断片の中に自分自身の姿を捜し求めてる。『asdfasdf』は、多くのミュージシャンが試みることのないような複雑な構造を持っていて、すぐれたメロディの“芯”が、その抽象的な音の重なりを支えている。デイの音楽の奥深いところから、悦びに満ちた熱が放射されてる。この計り知れない不思議なパワーを味わうためなら、この奇妙なアルバムを何度だって聴き返す価値があるんだ。

ライター : Ian Cohen
翻訳元 : http://pitchfork.com/reviews/albums/18963-the-hotelier-home-like-noplace-is-there/
翻訳者 : kei
2ndアルバム『Home, Like NoPlace Is There』のアタマでChristian Holdenはこれでもかと言葉を重ねる。もうちょっとハッキリ言おう。歌詞に使われている言葉は288にも及んでる。でも、それでもここにある最も決定的で、言葉を超えた瞬間は歌詞カードには載っていない。高々と掲げられたホーン、クリーントーンのギター、朗々と響く電子オルガンが歌うHoldenの周囲でくるくるとワルツを踊る。彼は窓枠の向こうで手を振る友達を見る。「キミがぼくをそこで呼んでいたんだ / ひとつ深呼吸をして、飛び降りた」。バンドの残りのメンバーがそれをめちゃくちゃに飾り立てる。「whoa-oh-oh!」。だが、それは瞬く間に消え去り、残りの3分半、それが不意に切れるまでHoldenは同じメロディーを執拗に繰り返す。「キミがくれたクスリはちっとも役に立たない / ぼくは何年も目を閉じるしかなかったんだ」彼はこう叫び、あえぐ。敗北感が沸き上がる。バンドはそれを避けることなく、爆発し、一秒ごとに膝を屈しそうになる。最後の1分、Holdenはすでにボロボロだ。辛うじていくつかの絶叫が聞き取れる。「握りしめていたモノがある / それを離してやれば良かったんだ / クソッタレ、それでどうなるって言うんだよ?」。その数秒後、トラックは無慈悲に断たれる。曲名は「An Introduction to the Album」。そして、この時点で僕らは歓喜の中にいる。
『Home, Like NoPlace Is There』の中で燃え盛る炎は消えない。そして、ウースター(訳注1)からやって来た彼らは時おり言葉を手放してしまうけど、だからって別に問題はない。僕らが耳を離すことなんかできないからだ。Holdenの歌は365日、24時間、誰かの目を必要としている。曲同士はカオスの中で絡み合う。浮かび上がるのは「もうどうにでもなれ」と暴れ、「苦しみから逃げようとして自分を傷つける」男の子だ。さて、そんな彼から午前3時に電話がかかってきたり、変な素振りが目立ち始めたらどうする? シカトするかい? ……なら、そろそろ葬式に着ていく服を選ぶ時間だ。実際のところを僕らは掴めない。でも、閉じきった部屋、散らばった錠剤、木漏れ日のような希望、叶わない約束、そこに佇んでいるもう声を上げることもできない子がいるんだ。
よくあるロック・ミュージシャンの話さ、だろ? 特にthe Hotelierのようなエモーショナル・パンクならもっとだ。Holedenの言葉はアルバムをめちゃくちゃに揺さぶる。ここで「ぼく」はギリギリのバランスで生きてる、弱虫の立場からずっと動けない。そして、コレが家族や友達でもどうしようもないことを分かりながら、イイ子になろうとする思いに挟まれ、もがくしかない。「The Scope of All of This Rebuilding」でHoldenが荒々しく突き刺すようなギターの上で歌う「そっちから関係はぶった斬ったろ / でも、繋がりが消えないんだ(原文 you cut your ropes, left the umbilical.)」には隠すことのない思いとこの二人を結ぶものがこびりついてる。無関心も過保護も心にあたえる痛みは同じだ。アルバムはどこを切っても罪悪感と後悔に血を流す。「Your Deep Rest」でも彼は本来の目的である葬式に身が入らない。最初のコーラスではただ居心地の悪さだけ浮かぶ。二度目には「他の家族の目線がぼくの肩にのしかかる」。
こういうのって君にはどうでもいいかい? だけど、君のお気に入りのClear Channel(訳注2)のチャートをよろめき、つまづきながらも「Your Deep Rest」っていうポップ・ロックが駆け上っていく。『Home, Like NoPlace Is There』は間違いなく感情に支配されたアルバムだが、果てしなくキャッチーなレコードでもある。HoldenのヴォーカルもEMOのスタンダードに沿っているーーハイトーンを出そうとして裏返り、かすれる声にトレーニングの影はない、でもとても魅力的だーー、けど、こうも言える、これまでシーンへと頭角を現してきたパンク・バンドもそうだったって。オープニングに続いて、大人数による合唱、コール・アンド・レスポンスで盛り上がり、それらをかき混ぜてFugaziの精緻さをバラバラにし(「The Scope of All of This Rebuilding」)、そこからいきなり駆け足でAgainst Me!や、the Weakerthans(訳注3)的なパンキッシュ・フォークを演じてみせる(「In Framing」)。これはたった5分の話だ。
曲、それ自体はバラエティに富んでるけど、『Home, Like NoPlace Is There』は拭いきれない破滅願望に何度もハマりそうになる姿を映し出している。鍵となる言葉が「In Framing」にあるーー「キミは繰り返し同じ場所をなぞる / 切り裂いて、また縫い合わせる / 例えば一人ぼっちなときに、例えばとてもさびしいときに」。それぞれのイカしたアレンジはある種のテーマの変奏だけど、コレは決して物語としてあるわけじゃない。「An Introduction to the Album」や、「In Framing」の前半で分かるようにHoldenは堂々と振る舞うことで落ち着きを保とうとしてるけど、衝動的に怒りをぶちまけてしまう「Life In Drag」とか、「The Scope of All of This Rebuilding」でそれはダメになってしまう。最悪なことをブチ撒ける歌が、結局は最高のアンセムとして響くんだ。力強いバラッドとも言えそうな「Discomfort Revisited」や「Among the Wildflowers」がそうだけど、Holdenはそこで一つのことを認める。友達といても消えなかった痛みはなんだったのかって。ーーきっと誰かと居ても独りであるってことは変わらないんだ。
ギリシャ語の「木」からとられた壮大なクローザー「Dendron」は木の枝の隙間から「Your Deep Rest」の景色を覗くような気分だ。もちろんコーラスには感傷的な告白が待ってる。「キミのさりげないそれがぼくの背中を押してくれた / 危ないものの一つすら見えてなかったんだ / だから、言うべきなんだ キミの足に絡まったソレ / ソレはぼくがやったんだ」。アルバムは最後に「An Introduction to the Album」のメロディーを調子を変えてまた鳴らす。ここはハッピーエンドじゃないし、終わりはまだ遥かにある。彼らは単に君をまた同じ場所へ連れてきただけだ。拳を構えろ。戦うべき明日が来ている。
『Home, Like NoPlace Is There』は倒れこんだままの君のケツを思いっきり蹴っ飛ばす。むしろそれ以外はできない、と言った方がいい。the Hotelierは戦っている、心底入れ込むこと、無知であること、そして自分たちのこれまでに対して。アルバムの冒頭で鳥たちは告げている「そんなものぶっ壊しちゃえ」と、たぶんこれは彼らのthe Hotel Yearとしての幸運なデビューにも引っかけてるんだろうけど、その世界は業界のお約束だかなんだかに囲まれてどうしようもなくなってる。彼らが自分たちの過去話(訳注4)でバラしてるように。今でもthe Hotelierはそうしたものを望むファンにちゃんと自分たちの音楽が届くよう戦い続けてる。だけど、その終わりに向けてHoldenが綴るように、最後には"emo now. ¯\_(ツ)_/¯"と肩をすくめてみせるように、この言葉は自称インディ・ロックのファンや、パンク・ファンなんかの足を遠ざけてしまう。ここに彼らが望んでいるものがあるんだけどね。詩的で耳に残るギター・ロックバンドはそれ自身も魅力的なインディペンデント・レーベルに所属していて、草の根のショウを通じて、大きなユメを最近は描いている。
誰がなんて言おうと、サウンドや立ち位置、その精神面においてthe Hotelierはパンクなんだ。だから、『Home, Like NoPlace Is There』もたまに「良く出来た」なんてワクを蹴っ飛ばして、興奮のまま暴れまわってしまう。ダメなところも上げよう、「Housebroken」はメタファーであることに気を取られ過ぎてるし、冴えないプロダクションの為にせっかくのアレンジが力をちゃんと出せてなかったりする。ーーだけど、これは始まりだ。自分たちが持ってるものに彼らは気づいた。アルバムで鳴らされるサウンドはthe Hotelierがそこにあったモノを打ち砕いてるそれだ。ここに残ったのは彼らがもっとスゴいモノを建てるための更地だけだ。
訳注1 マサチューセッツ州第2の都市であり、20万人の人口、全米トップクラスの大学、教育機関を備える。近年の無秩序な都市開発が問題になることもあり、1999年には起こった火災により、消防士6名が殉職している。
訳注2 Clear Channelは全米のラジオ局をインターネット上で視聴できるインターネット・インフラ・サイト。母体はマス・メディア会社のiHeartMedia.。現在は850局のラジオ、25カ国に及ぶ屋外広告の請負、40を超えるテレビ局を傘下に収めている。180のアメリカ、カナダ圏内ラジオ局でのチャートをまとめたMediabaseという音楽チャートを実施している。
訳注3 Against Me!は1997年にフロリダ州ネーブルズでLaura Jane Graceによるソロ・プロジェクトとして始まる。その後、2002年頃に四人組バンドとして落ち着き、現在までメンバーチェンジはあれどコンスタントにアルバムをリリースし、精力的に活動している。サウンドとしてはパンク・ロックにカントリー、ブルースといったアメリカン・ルーツ・ミュージックを取り込み、フォーク・パンクと呼ばれることもある。またLaura Jane Graceは2012年に性同一性障害をカミングアウトし、性転換後に旧姓のThomas James Gabelから改名している。the Weakerthansは1997年にカナダ・マニトバ州ウィニペグで結成されたインディ・ロック/パンク・バンド。John K. Samsonを中心に現在までに4枚のアルバムをリリース、いずれも高評価を受けている。カナディアン・バンドであるが音楽性としてはカントリー、アメリカン・ロックの影響下にあるバンドと捉えられており、Johnによるメッセージ性の強い歌詞も高い評価を受けている。
訳注4 彼らがこのアルバムリリース前に自身のTumblr上に公開した文章には自身のバンドがファーストアルバムをリリースして以降のレーベル関係者との軋轢、音楽ビジネスへの失望、バンドの歴史などを赤裸々に明かしている。その文章の締めとしてChristianは「Apparently we are emo now. ¯\_(ツ)_/¯ I hope you start a band or do cool shit.(今のぼくらはやっぱり"EMO"だろうから¯\_(ツ)_/¯。 そして、いつか君が始めたバンドか、生み出したなにかに出会えることを願ってる。)」と結んでいる。
付記
年間BESTに人の意見をつけてもらう企画 第5弾&EMOリバイバル・シリーズ。
個人的にこれまで読んだIan Cohenのレビューでも屈指の素晴らしさ。彼の2014年BEST Albumであるだけあって、込められてる熱量が半端ないのに加えて、アルバム全体の流れ、歌詞、バンドの歴史、EMOの立ち位置なんかをもの凄い技量で収めて見せるというその筆力に圧倒されました。
The Hotelierの生み出したこのアルバムはSunny Day Real Estateの『LP2』に匹敵するほどのこもり方をしながらも、それをぶち壊していくのです。読むたびに、聴くたびに深まる意図。ぜひとも、アルバム自体と一緒にどうぞ!
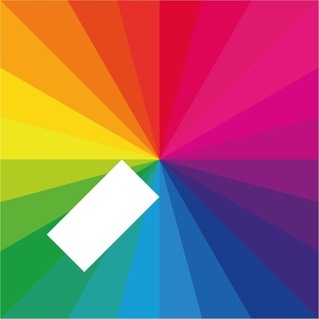
ライター:Mark Richardson
翻訳元:http://pitchfork.com/reviews/albums/20458-in-colour/
翻訳者:hira
サンプラーは記憶装置だ。記憶は、まさに文字通り鍵となるスペックのひとつで、一瞬でどれほどの音情報をその「心」に包括できるかを計っている。そして同時にメタファーでもある。音を捉え、新しいコンテキストへと変化させプレイバックする時、特定の音を演奏するのと同じように、元の音楽へと紐付かれた記憶を「演奏」している。Jamie xx として世界的に有名なプロデューサー Jamie Smith は、サンプリングアーティストであり、メモリーアーティストである。彼はこれまでどっぷり浸かってきた音楽と、そこに埋め込まれたつながりで、それを実現している。だから彼の音楽を聴くと、単なる部屋の中で演奏される音を聞いているのではなく、彼の聴いているもの、彼の耳に入ってくるものを私たちは聴くこととなる。彼は特定の音に記憶を感じ、(それは時には初めて体験するような音もあれば、すでに受け継がれた音もある)新しく、パーソナルなものへと変化させるのだ。
Jamie xx のソロデビューアルバム『In Colour』の噂は数年前からあった。2011年、デビューシングル「Far Nearer」に続き、 リミックス「We’re New Here」では Gil Scott-Heron とコラボもしている。The xx での仕事とは明らかに異なり、両端にまたがる傘のような広い想像力と多彩な感性を手に入れている。プロデューサーとしての Jamie xx の実力は、The xx の2作目『Coexist』ではあまり発揮されなかった。立派な作品ではあったが、 Jamie xx のセンスの幅を知ってしまうと、その知識をメインのバンドの限られた美的範囲と両立させるのは難しくもあった。しかし今作はうまく融合されている。彼の素晴らしい点のひとつに、各プロジェクトを一度きりのチャンスのように時間をかけて行うことが挙げられる。『In Colour』もそうだ。それはJamie xx の6年間の煌びやかな結晶であり、彼が携わってきた要素がすべて集約されている。ムーディーなバラッド、フロアに広がる爆音、ヴォーカルとの開放的で予想外のコラボレーション。それらを輝くミラーボールへとぎゅっと詰め込み、その光の破片に私たちは照らされる。
皆とって特別な何かがある、というのがレイブの重要な考え方だ。レイブはかなりファッショナブルな時もあったが、当初からずっと平等主義なのだ。ダンスフロアのプラトニックな理想は、完璧に実現したことは当然ないのだが、ダンサーが平等に集まるということである。皆がそれぞれの旅の途中で、誰かにジャッジされることもなく、最高のタイミングのドラッグでこの非現実的なビジョンは現実となる。Jamie xx の音楽はヒップで最先端、そしてとてもエモーショナルになることで、こうした心を捉えている。それは私たちを感じさせる「クール」な音楽で、その装置は脆い。
『In Colour』には、開放的で親しみやすいと同時に巨大でアンセミックになる道筋がある。オープニングトラックの「Gosh」で最初のステージは用意される。ひとつのループは次々と繋がれ、新しいグルーヴの重なりは空間へと放出されて空高くそびえ立つ殿堂を作り上げる。もう体を動かさずにはいられない。そして最後の固い絆が空間へと放たれると、まるで新しい楽器を手に興奮したような、抑え気味で少しぎこちないシンセソロが始まる。まだ興奮と驚きが残るようなキーボードが落ち着くと、『カールじいさんの空飛ぶ家』のような空に昇っていくたくさんの風船によって、突如音の塔が覆われていくのだ。
この見晴らしのいい場所からの景色は決して消えない。「Sleep Sound」はFour Freshmen の「It’s a Blue World」からサンプルを拾い、丁寧に細かく切っていく。The Field の Alex Willner がThe Flamingos の「I Only Have Eyes for You」でやったようなものではなく、溺れそうな気配すらある水の夢に浸り、濾過されたような声を震わせる。「I Know There’s Gonna Be (Good Times)」はラッパーの Young Thug とダンスホールボーカリストの Popcaan をフィーチャーしている。その情報を最初に聞いた時は、3人のコンビネーションに不安もあったが、結果ぴったりと合っていた。独特のリズムで世俗的な対句を歌うThug は喜びではちきれそうで、Popcaan は音楽を細かく砕き、Jamie xx のジャングルヒーロー達のラガへの橋を建てている。アルバムが進むにつれて、肥えた耳によって繋がれたスタイルとテクスチャを通って Jamie xx は動いていく。
Jamie xx のバンドメンバーとのコラボは3曲。例えば「Good Times」では「曲」と「トラック」の間にまたがるのがどれほどうまいかを痛感するだろう。Oliver Sim をフィーチャーした「Stranger in a Room」は(本当に素晴らしい)The xx の曲に成りえただろうし、バンドから出来上がったかもと思える唯一の曲である。「SeeSaw」での Romy のメロディは、スペアギターとドラムの代わりにJamie xx のブレイクビートと脈打つシンセで囲まれ、宇宙のような無限の壮大さを感じさせるなかで、静かに、そして熱望も混じって告白される。ジャズドラマー Idris Muhammad の「Could Heaven Ever Be Like This」の絶妙なサンプルが使われた「Loud Places」は「SeeSaw」と対照的な曲である。だが、「Loud Places」のサンプルはより暖かく、寛容的で、 Morrissey も羨むような孤独と欲望をクラブを舞台にシンプルな歌詞で描いている。「騒がしい場所へ行く/誰かを探すため/一緒に静かにいてくれる誰かを」
一瞬で全てに圧倒される感覚と、細かなディテイルの中までのぞき込みたいという欲の二つの感情の衝突は、『In Colour』の生の力となっている。アルバムの後半、「Gosh」の裏面ともいえる「The Rest Is Noise」で勢いは頂点に達する。パーティーは裏返しになり、自由奔放な叫びは影を潜め、切望が打ち寄せる。まるでアルバムが始まった場所へと戻るかのように、「Gosh」のシンセに合わせて小さく揺れうごく。それを聴くと、スチールドラム主導の、本作で最も控えめなトラック「Obvs」についての Jamie xx のコメントを思い出す。彼は楽器に魅了され、定期的にそこに戻り、その魅力についてこう表現していた。「とてもメランコリーな音を作ることができる。でも同時に、天国も思い浮かぶんだ。」『In Colour』がどんな作品かを示す悪くない表現である。どんなスリリングな瞬間も、すべてはもうすぐ終わってしまうことが分かっている切ない悲しみを覆い隠すことは決してできない、騒がしいパーティーのようなアルバムなのだ。

ライター:Jayson Greene
翻訳元:http://pitchfork.com/reviews/albums/20313-the-ark-work/
翻訳者:Gasse
初めてLiturgyの『The Ark Work』を聴いた時は、その巨大な音の塊に困惑させられてしまった感じだ。ギターとパーカッションに合わせて、ホーン、ストリングス、絶え間なく打ち鳴らされるグロッケンシュピール、おまけにパグパイプまで、全ての楽器がいちどに奏でられる。11ものブラウザのタブが展開されて、自動実行状態にあるみたいに。あるいは、走り去ったオートバイのせいで、1区画分の自動車の警報装置がいっせいに鳴り響くみたいに。Liturgyは本作をそんな風にデザインしたのだろう。バンドの中心人物であり、『The Ark Work』のメイン・アレンジを手掛けたハンター・ハント=ヘンドリクス Hunter Hunt-Hendrixはインタヴューで、彼の頭の中に閃いたサウンドについて語っている。『The Ark Work』というアルバムは、彼が私たちリスナーと分かち合おう思った作品、という表現がいちばんしっくりくるのだと彼は言う。本作における彼の意図はあまりに巨大で、ブラック・メタルというジャンルの壁を内から破壊するほどの圧力を生み出した。本作を聴いていると、まるで誰かの頭を割って覗き込んでいるみたいで、消滅と復活というテーマに関心を持つこのバンドのイメージにはぴったりだと思う。
2度目に『The Ark Work』を聴いた時は、ドスッ、とはっきりと聞こえる鈍い音を立てて行われる優雅な鞭打ちのような印象を受けた。2009年の『Renihilation』と2011年の『Aesthethica』という前2作品でLiturgyは、ハント=ヘンドリクスの壮大なアイディアに楽曲という形を与えようとした。一方、本作では『The Ark Work』というパッケージに包まれた完全に理解不能な図形を、楽曲の形式へと具体化しようとしたのだ。57分に及ぶ『The Ark Work』の長さや壮大さは、過去の作品以上に交響曲、それもブルックナー Josef Anton Brucknerの作品のような、長大でゲルマン的なものに近い。明確な意図を持って配置された長大な楽曲は、混乱と倦怠との絶妙なバランスへと調整され、それらはアルバムの進行とともに次々と壁へ押し寄せ、意気揚々とそれを乗り越えていく。
山の斜面にぽつぽつと花を咲かせる高山植物のように、いくつかのテーマが繰り返し現れ出てくる。アルバムの2曲目、最初のヴォーカル入りのトラックである「Follow」は、対位法で奏でられるグロッケンシュピールで始まり、ベースラインのペダルトーンに先導されて進んでいく。それは、壊れやすく非現実的なまでの美しさだが、曲の最後で唐突に打ち切られて終わる。同じテーマが、その後のいくつかの曲にも再度現れる。「Follow II」と「Haelegen」ではオルガンで奏でられ、最後の「Total War」でもう一度現れる。それらは言うなれば、混沌の中に存在する腰を落ち着けてじっくりと考えることのできる空間のような役割を担う。
有り体に言って壮大で、なおかつ聴き手を惑わせるようなこのアルバムにおいて、全編を通じて配置されたこれらのテーマはリスナーにとっての目印の役目を果たす。『The Ark Work』という作品は、豊かなハーモニーを持つ作品であるが、とてつもなくスローな作品でもある。言ってみれば、ガラスだって技術的に言えば液体の一種なのだと指摘するようなものだ。本作で最も心を揺さぶり、盛り上がる箇所を聴くためには、かなりの苦痛を耐え忍ばなければならない。「Follow II」では、管弦楽器がマーラー Gustav Mahlerのオーケストラの弦楽団の上を舞う鳩のように、Liturgyの音楽を引き上げる。地上から数インチ浮いたところに吊るされて、苦痛にうめき、引きちぎれて中身がこぼれ出してしまうかのように思われるのだが、継ぎ目が破れて中からこぼれ落ちてくるのは、ハント=ヘンドリクスの小さな声だけなんだ。
この、ありえないほど巨大な存在が宙吊りになっている様を見ているかのような感覚は、『The Ark Work』において最もスリリングな面であり、アルバム全体を通して2~3回現れてくる。この箇所を聴いていると、ハント=ヘンドリクスの自らに鞭打つような渇望が正当化されたかのように思える。Liturgyというバンドはブラック・メタルの系譜ではなくて、苛酷でとてつもなく極端な音楽の追求に嬉々としていそしむバンド、Swansの後継者になろうとしているんだ。『The Ark Work』の名曲たちの持つ狂ったエネルギーは、ヴェルナー・ヘルツォーク Werner Herzogの『フィッツカラルド』に影響を受けているかもしれない。そして、ヘルツォークの創作の原動力である“狂った天才/天才的な狂人”というダイナミズム以上のものを、ハント=ヘンドリクスは持っているんだ。両者に共通する点として、プロジェクトの始めにこんな疑問が出る。“こいつ、マジなのか??”
『The Ark Work』には、ヘルツォーク作品との不幸な類似点がもう1つあって、むしろこっちの方がはっきりしている。眼前に広がる壮大な光景を眺めるためには、たまにイラッとくる“創作者の声”が聞こえないようにブロックしておきゃなきゃならない、という点だ。前作でのハント=ヘンドリクスの、プレゼントの包み紙を破るようなスクリームには、衝撃と奇妙な繊細さが同居していた。一方『The Ark Work』での彼は、ほぼ全編を通して、変化の乏しい一本調子でぶつぶつと呟くだけだ。そのせいで、初めて聴いた時の印象は薄まるし、かといって何度も聴くとその深みが理解できるという類いのものでもない。たぶん彼は、トランスめいたオカルト的雰囲気を狙ったのだろうし、実際彼はかつて、Three 6 Mafiaの三連句のフロウに影響を受けたと語っていた。「Quetzalcoatl」や「Father Vorizen」の長い呪文めいた一節を聴くと、彼の本来の意図はこのリズムを取り入れることにあったのではないかと思えるのだが、結果として、ある音楽が元々属していたジャンルからどれだけかけ離れたものに変化し得るか、ということを端的に例示した楽曲となった。
ハント=ヘンドリクスのヴォーカルは、しばしば耐えられるレベルを超えている。そう述べたとしても狭量とは言えないだろう。「Father Vorizen」での、ほぼ音程がなくリズムすらもなく、しつこく繰り返される呟きを聴いていると、イライラして彼を引っ叩いてやりたくなるだろう。なぜって、他の楽器の巨大な存在感に対すると、彼のヴォーカルは全体のミックスの端の方に細く折り畳まれて置かれているみたいで、そのせいで彼のヴォーカルは、炎を燃やしてトランス状態になっているカルト・リーダーと言うよりは、街角でぶつぶつとつぶやいている人みたいに聴こえてしまうからだ。"知覚のドアは開いたり閉じたり The door of perception will open and close/希望は理性とともに、不確実な関係性の中に在る Hope will exist in a problematic relationship with reason/リビドーの産むエネルギーはガラガラががらがら鳴るみたいにぐるぐると渦を巻く Libidinal energy will whirl round like a rattle rattling/心臓は物言わぬ骸となり、粉々に砕け散る Heart will stopped bones will shatter shattering,”ハント=ヘンドリクスは「Quetzalcoatl」で呻くようにそう歌い、彼の中途半端な思考の開陳のような一撃が、恐ろしいほどすぐ近くを掠めるように感じられるんだ。
この輝かしく、波紋を広げているバンドに対する評価としてはフェアでないかもしれないが、同世代のミュージシャンの中でもずば抜けて直観的で、スリリングで、音楽的に優れたドラマーであるグレッグ・フォックス Greg Foxがこのバンドを支えていて、ハント=ヘンドリクスの哲学の真髄を、当人以上に純粋に表現しているんだ(『Aesthethica』でもそうだった)。Liturgyは恐ろしいほどのパワーと気迫、そしてエネルギーをこのアルバムに込めたが、その結果として10回以上聴くと退屈しか感じられない作品ができ上がってしまった。難解なコンセプトが根っこにあるものの、この『The Ark Work』というアルバムには、全編を通して興味深い新しいアイディアが端的に示されている。「Fanfare」から「Quetzalcoatl」までの冒頭の5曲は、畏敬、恐怖、混乱、歓喜、絶望といった感情を呼び起こす。だが、この時点で『The Ark Work』はまだ折り返し地点にも到達していない。そこからは、悶え苦しむ後半戦の始まりだ。ただひたすらに疲労させられ、楽しみは失われていく。これは、本作の壮大さの負の面と言える。あまりにも作品を引き延ばしすぎると、終盤の方で退屈になってしまうのは避けられないことだよ。
【訳者コメント】
噂の問題作のレヴューを訳しました。個人的にはとてもおもしろい作品だと思っていて、メタルではなく、ポスト・ロックとかエクスペリメンタル・ロックの類いだとして聴くと楽しめると思います。
Hang on tight while we grab the next page
https://igai.bokepmobile.site https://wvhe.waihui.online https://rqnh.qipai.online https://fqps.workpolska.online https://rjyx.haychill.site https://kgtp.lexu.site https://qffx.bokepmobile.site https://negw.qipai.online https://tmjs.qipai.online https://vihk.lexu.site https://hehs.frisuba.online https://iyas.rubberducky.site https://frnx.ophimhd.site https://idqk.bokepmobile.site https://wshd.lexu.site